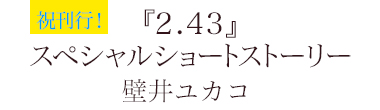去年と来年 ~ボールの話~
ボールが一つ、部室の共用ロッカーの奥に何故かしまいこまれているのを見つけたのはたまたまだった。バレー部所有の練習用ボールはナイロン製のボール籠に全部放り込まれて、練習時以外は部室の片隅で場所を取っている。試合の日はボールバッグに詰めて大会会場まで手分けして担いでいく。試合前の練習時間に使うためだ。
「なんでこんなとこに一個だけ……」
不思議に思いつつ、黒羽はロッカーに腕を突っ込んでボールを掴みだした。
「ん? ミカサ製?」
青と黄色の革が張りあわされたボールだった。しかし新品のときはぴかぴかしていたのだろう表面には無数の細かな傷が入り、ディンプルは磨り減って、鮮やかな青と黄色のコントラストも部員たちの日々の手垢にまみれてすっかり褪せている。
今年度の公式大会における男子の使用球は別のメーカーだ。
「なんでミカサがこんなとこに一個あるんですか?」
「あーそれ、去年の一年がパクってきたやつやろ」
さらっと答えたのは三年の青木だ。「パクったって……どこからです?」犯罪の臭いがする単語に黒羽は眉をひそめた。
「持って帰ってきたんはおれらですけど、わざとパクったんでないですって」
「大会んときどっかで紛れ込んだんに気づかんまま持ってきてもたんですよー」
「返そうにも接点なかったですしね……」
去年の一年、つまり今年二年の内村、外尾、棺野が順に釈明するようなことを言った。
黒羽は両手のあいだでボールを半回転させた。ボールの傷みとともに文字も掠れてはいるが、『福蜂工業』と油性マジックで署名されていた。「ああ……」と黒羽は納得して目を覆った。
福蜂工業高校。全国大会最多出場の伝統を持つ県内最強チーム。万年一回戦負けが常の弱小チームだった清陰バレー部とは、“去年”はたしかに接点がなかっただろう。
「うちにずっとあってもしゃあないし、黒羽、今度タイミングみて返しとけや」
「えー! おれに尻ぬぐいさせんでくださいよ。だいたい“タイミング”なんていつあるんですか」
無茶振りされて黒羽は抗議の声をあげた。加勢を求めてもう一人の一年である灰島に視線を投げたが、練習に直結することなら掃除でも準備でもなんでも面倒がらずにやるくせに、このマイペースな天才はこういう理不尽な押しつけには知らんぷりして菓子パンで頬を膨らしていた。
“タイミング”は十二月の末にあった。十一月の代表決定戦で福蜂を下して全国大会への切符を手にした清陰は、福蜂が毎年この時期にOBの大学生らと行っている合同練習に呼んでもらう機会を得た。
とはいってもおそらく福蜂も清陰がボールを一つパクっていたことになんて気づいていないだろう。福蜂のボール籠にこっそり紛れ込ませれば自動的に返せるだろうと計画していたのだが……。
体育館にだされている福蜂のボール籠には白・赤・緑の配色の別のメーカーのボールが積みあがっていた。この中に青と黄のボールをまぜても、どう考えてもあっという間に不審がられる。部室には去年使ったミカサのボールもあるのかもしれないが無論部室まで忍び込めるはずもない。
万事休す。練習試合の合間を見つけてボールが一つ入ったナイロン袋を抱え、どこに置いて帰ろうと途方に暮れる。うっかり捕まえてきてしまった野生のガチョウでも放流する場所を探す気分である。同じ毛色の仲間のもとへ帰ることができない傷ついたボールにこのままでは愛着がわいてしまう。
あ……。ふと思いついて頭上を見あげた。清陰の体育館もそうだが、福蜂の体育館にも手すりがついたギャラリー(通路)が壁に沿ってぐるりと設えられている。練習中に飛び込んだボールがその上にいくつも転がっているのが見えた。どの学校の体育館でも必ず見られる風景だ。
おまえを放す場所、見つかったぞ。胸に抱いたボールに心の中で話しかけるという我ながらだいぶ痛いことになりつつ、ギャラリーに登るハシゴに足を向けた。
ハシゴの下でボールをそっと袋からだし、ハシゴに手をかけたときである。
「なあ」
背中に突然声をかけられて黒羽は思わずボールをお手玉した。取り落としたボールがてんてんと床を跳ねていき、つや消しの銀色の松葉杖の先にこつんとあたった。
「うげ。三村……さん」
「おまえ、おれ見るとそーゆうリアクションするよな」
福蜂工業バレー部主将── 一ヶ月前の代表決定戦の敗退をもって引退したので『元』主将、三村統。まわりがみんな練習着姿の中で一人だけ福蜂の制服姿で、ワイシャツの袖をまくった両手に松葉杖をついている。一八九センチの長身を支えるアルミ製の松葉杖はたぶん一番長いところに調節されている。
「さっきからなんかキョドってんなーと思って見てたら……」三村が松葉杖の先でボールを軽く転がした。「あ」と黒羽。マジック書きの署名が上向いた。
……バレないように返そうとか姑息な手段を巡らせないで最初から普通に返しておいたほうがましだった。赤面して黒羽はボールを拾いあげた。
「……というわけで、一年間パクっててすんませんでした」
いきさつを話し、ボールを差しだして頭を下げた。
「あー。まあ県大会で毎年うちのボールなくなるんやわ。なんか他のガッコがありがたがって、転がってきたら持って帰るらしいで。むしろわざわざ返してきたの清陰が初めてでねぇんか」
「え……ほーなんですか」
福蜂にとってはたいしたことではなかったようで黒羽は拍子抜けして頭をあげた。
左手の松葉杖に体重を預け、右手で三村が黒羽の手からボールを掴んだ。片手で軽く放りあげて一回転させ、器用に手の上に載せる。三村のチームの名が刻まれたボールが、黒羽が持っていたときよりもどこか安心したような顔で本来あるべきところに収まった。
「ほうか。去年から清陰にあったんか。ほしたら“こいつ”は全国を見てえんボールなんやな……」
ボールを見下ろし、微笑を浮かべて三村が呟いた。
一瞬きょとんとしてから黒羽にもその意味がわかった。
去年清陰の部室に拉致されていなければ、このボールは他の仲間のボールとともにインターハイにも春高にも行けたのだ。公式大会の試合球のメーカーは一年ごとに交代することになっている。三村が高校三年間でミカサのボールと一緒に全国大会に行く機会は去年、二年生のときしかなかった。
全国を見られなかったボール、か。この人でもそんなふうに考えるんだ……と思ったら、自分があれこれ巡らせていたボールへの想像もそんなに恥ずかしくなくなった。
「あの、そのボール、連れてきましょうか……春高に」
年明けの一月、高校生バレーボーラーにとっての甲子園とも言われる『春の高校バレー』が東京で開幕する。清陰は福蜂にかわり福井県代表として初めて全国に挑む。
「あっえーと、お守りがわりっちゅうか、うちにとっても心強いっちゅうか」
思いつきで言ったものの突然変な申し出をしただろうかと慌てて言い繕った。
「はは。やめとけや。最高位が全国ベスト16のお守りなんていらんやろ」
三村が乾いた声で軽やかに笑い、似つかわしくない自虐を言った。「工兵ー」と後輩を呼ぶと「あっはい、統先輩」と福蜂二年の戸倉が駆けてきた。二人きりで話していたのを見て牽制するように黒羽を睨んでくる戸倉に三村がボールを投げ渡した。
「部室に戻しといて」
「なんでミカサがこんなとこに一個あるんすか?」
黒羽が部室でボールを見つけたときとそっくり同じことを口にして戸倉がボールを受け取る。空になった手に三村が松葉杖を持ち直し、
「来年それ、全国に持ってけや」
と何気ない口調で戸倉に対して言いながら、意味ありげに黒羽に横目をよこし、唇の片方の端で薄く笑った。
──自虐的になんてなってないじゃないか。思いっ切り挑発してきた、この人。
体育館履きの足音の他にトン、トン、と硬い音を残して三村が離れていく。向こう側の壁際で座って休憩していた灰島が訝しげに三村の姿を目で追い、戸倉と二人で残された黒羽のほうへ目を移した。
ボールを小脇に抱えた戸倉が舌打ちし、
「よう話わからんけど、いい気になってんなや。おまえらの天下なんて今だけやぞ。来年またすぐうちが取り返すでな」
と顔を突きつけて凄んできた。目の端で灰島が床に手をついて軽く前傾姿勢になった。加勢がいるか?という顔で見つめてくる。
なんだか血の気が多い奴ばっかだなと黒羽は呆れる。呼んでもらってお邪魔してる相手のホームで喧嘩を買う気はないぞ。
これくらいで灰島の加勢は必要ない。
「戸倉さんはずっとバレーやってたんですか?」
一見脈絡のない質問をすると、「ん? ああ、小学生んときからやな」とやや面食らいながら戸倉が胸を反らした。
「ほーなんですか。おれは中学んときグレてたんですよー」
従兄弟の腰巾着だっただけなので実際は黒羽自身はグレていたというほどではない。だがいわゆる田舎のヤンキーたちと顔見知りだったのは本当だ。戸倉のように根っからの健全なスポーツ少年に凄まれても、正直さほど怖くはない。
身長はほとんど同じだ。鼻先で押し返すように顔を突きだすと戸倉のほうがわずかに怯んで顔を引いた。
「うちはまだ“今年”が続いてるんで。来年の話は、来年また」
痛烈な挑発で返した。目と鼻の先で戸倉の顔が紅潮した。
来年とか卒業後とか、みんなが先々まで考えていることに黒羽としては実はちょっと辟易している。まだ高校一年なのに。
「まずは春高、全力でぶつかってきます」