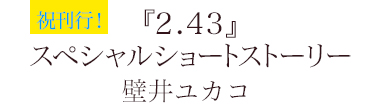男子バレー部が全国大会初出場! 清陰高校を取材しました!
黒羽にとってはなんていうことはないジャンプで天井に届き、右手の中三本の指で天井の埃を擦って床におりると、一年C組の教室が歓声と拍手でわいた。
親しいクラスメイトと「イエーイ!」と賑やかにハイタッチを交わす。一八六センチの黒羽が掲げた手に大半のクラスメイトは背伸びをしたりぴょんと跳ねたりして手を打ちつけることになる。そんな「バレー部のエースの学校での日常」を教室に入っているテレビカメラが映している。
日常っていっても別に日常的にこんなことやらんけど……。とはいえそれこそ「日常」では黒羽はクラスの中心人物でもなく、平凡にやり過ごしている一生徒でしかない。テレビ映えのためにこれくらいのパフォーマンスをするのはまあやぶさかではない。部のイメージアップに協力するようにと青木にも言い渡されている。
今日は福井県ローカル局のフクロウテレビが校内に撮影に入っている。甲子園の特別番組なんかで見たことがあるああいうやつがとうとう自分の学校に来たのかと、期末試験も乗り越えて冬休みを目前にした校内はざわざわと浮き足立っていた。
「三年生の小田くんは部員からの信頼も篤い男気あふれるキャプテンです。バレーボール選手としては身体は大きくありませんが、お弁当は大きいですねぇ! ……とかいって」
昼練に備えて午前中の休み時間に教室で早弁を済ませる小田の「日常」にテレビカメラがまわる。
「なんや今のナレーション。おれの弁当そんなでかないやろ」
三年F組の教室までカメラについてきた黒羽がこっそり勝手なナレーションをつけていると自分の番の撮影を終えた小田が近づいてきた。
「実際放送されるときのナレーションとそんな外れてえん自信ありますよー」
あと小田の弁当はでかいと思う。
「次誰んとこですか?」
「パソコン室で青木やって」
「なんでパソコン室なんですか?」
小田も一緒になり、桃太郎がおともを増やしていくみたいにテレビクルーのあとをなんとなくついていく。
パソコン室は情報の授業で使うノートパソコンが並んだ教室である。人のいない教室の一席でパソコンに向かっている青木をカメラが映す。椅子に斜めに座り、サラブレッドを思わせる長い脚を机の外側で組んで物静かにキーを叩く一九三センチの長身がなんだか腹立たしくなるほど理知的な雰囲気を醸している。
「青木先輩、自分のイメージ作りばっか卑怯やないですかぁ?」
小田とともに戸口でその様子を覗きつつ黒羽はドン引きでぼやいた。
カメラが青木の背後にまわって作業中の画面を映し、「なにを書いてるんですか?」と尋ねた。
「はい、合宿所の建て替えと第二体育館の新設の嘆願書です。今回の全国大会出場が奇跡にならんように、後輩たちにまともな練習環境を残してやりたいので……」
いかにも殊勝な顔で青木がカメラに話すのを見て「ようやるな!」と黒羽は思わず小声で突っ込んだ。なんだって部のイメージアップなんてことを言いだしたのかと思ったら、そういう目論見があったのか。
「忙しいやろにそんなことまで考えてくれてたんか、青木……」
「いまいち素直に感動できんのですけど……。転んでもただでは起きんような人ですよね」
ブレザー姿で二年C組の前の廊下を行き交う生徒たちの中を、UVカット仕様のパーカーを着込みフードを目深におろした細身の生徒が歩いている。校内では見慣れた棺野の「日常」の恰好なので新学期ならまだしも年末になった今さらぎょっとする生徒はいないが、その様子を追っているカメラのほうを気にして生徒たちがちらちらと振り返る。
「えっ今のテレビ? いややー映ってもた?」
「文化祭でドラキュラやってた人、男バレやったんやー」
撮影を覗いている黒羽とすれ違ってからカメラに気づいた女子生徒たちがはしゃぎながら離れていった。
「ああいうとこ撮らんでも、バレーやってるとこだけ撮ってくれたらいいのに」
棺野が自分の番から解放されると二年A組から見に来ていた女バレの末森が不満を呈した。フードをあげた棺野が「まあそういう番組やで」と苦笑して末森をなだめる。鼻筋から頬にかけて薄くそばかすが散った色白の顔がフードの下から露わになった。
「バレーやってるとこは本番の春高でも見せれるし。コートに立つときは他の選手となんも変わらんから。色眼鏡なしで『バレーやってるとこ』だけを見てもらえるよ」
末森がきょとんとし、ちょっとばつが悪そうに肩を竦めた。
「……いいプレーもやけど、あかんプレーも色眼鏡なしで評価されるんやぞ。しっかりやらんとね」
勇ましく発破をかけられ、「ほやね。腹くくってやります」実は内面は部内一男前な棺野が穏やかに、不敵に微笑んだ。
「灰島の番って黒羽の前に終わったんでなかったんか?」
「はい、最初に撮る予定やったんですけど、あいつ二時間目の休み時間ずっと机で寝てたとかで……。まだ撮れ高なしやそうです」
「協力しろっちゅうたやろが、あいつは……」
男子バレー部の全部員八名のうち七名が自分の番をなんとかつつがなく終え、肩の荷がおりた顔でみんなが最後の撮影にまわされた一年F組の戸口に集まった。
「灰島くんってクラスではどんな人?」
灰島一人だと撮れ高に不安があるのでクラスメイトにインタビューする形式になったようだ。灰島を真ん中にして黒板の前にクラスメイトが並んでいる。クラス内ではやはり背が高く、頭が小作りなので頭身は高いが、薄い目鼻立ちにお洒落感のない細い銀フレームの眼鏡をかけた灰島は教室にいるときはなにも際立った存在ではない。部活時以外はスイッチがぷっつり切れた顔でつまらなそうに突っ立っている。あれではイメージアップの対極である。
「んー。有名人やげなー」
「うん。有名人。入学したときクラスで一番はよ名前覚えられたで」
「へえ! 人気者なのかな」
クラスメイトが口々に言って頷きあうとテレビスタッフがほっとしたように声を高くした。戸口で見守っている男バレの仲間たちにも「ほお。あいつクラスでちゃんと人望あるんか?」と微笑ましげな空気が流れたが、
「人気者っちゅうかー、入学式の三日後くらいに三年の男バレの人にキレられて」
「ケツ蹴られて机の列突っ込んでー」
「それが強烈やったで一気に有名んなって」
「あと球技大会んときも他のクラスの奴と喧嘩んなってたよなあ」
「おれも球技大会バレーやったけど、ほーいえば練習んときもなんかラグビー部の人に肘鉄食らって」
クラスの中では笑い話のようで次々にネタが飛びだして盛りあがる一方で、「テレビの電波に乗せれるエピソードがねぇんかあいつには……」「灰島のせいで放送自体なくなったらおれの計画が台無しやぞ」とこっち側では男バレ一同が頭を抱えた。
「あと二学期んなったら男バレなんか事件起こして活動自粛になっててー」
「それはおれのせいじゃねえ」
顔を引きつらせて黙っていた灰島が間髪をいれずに凄みの利いた声で反論した。灰島の目つきがなんかもう放送事故レベルの凶悪さである。
「あれだけは百パーおまえのせいや」
とこっち側で黒羽がほうぼうから小突かれて「すんません……」とうなだれる。教室内ではテレビスタッフがドン引きして「な、なにかもうちょっといいことない?」と他の生徒にも話を振った。
「おれ、灰島のおかげで体育のバレー苦手やなくなったよ」
と、端にいた男子生徒がおずおずと口を開いた。
「ジャンプするタイミングとか、手のどこで打てばいいかとかコツ教えてもらったら、スパイクちゃんとミートできるようんなって。部活じゃすげぇレベル高ぇことやってんのに、ぜんぜんできんおれのレベルにあわせて教えてくれました。天才ってなんか人に教えんのは下手っちゅうイメージやけど、灰島は教えるん上手いと思います」
カメラを向けられてキョドりつつもはにかんで証言したクラスメイトに灰島が目をしばたたかせた。
バレーコートに入れば恐るべき集中力で常に鋭くなにかを睨んでいる目が泳いで唇がむにゃむにゃし、
「スパイク打てるようになったら絶対バレー面白くなるから……」
人が変わったようにぼそぼそ言ったがまんざらでもなさそうな笑みがほんのり浮かんだ。
こっち側では部活の仲間たちが顔を見あわせた。
「放送中止は免れたんでねぇんか」
と小田が愉快そうに笑った。
「撮れ高、大丈夫そうっすねぇ」
部員全員の撮影が無事終わったと思ったら、あともう一件撮りにいく先があるとのことだった。
「へっ? うちですか?」
黒羽は初耳だったが今夜のアポを取ってあるそうだ。見事な達筆の横断幕をしたためられた黒羽くんのお祖父さんにコメントをもらいにいく──とのことで、夕方の部活後、案内がてら学校から紋代町までテレビクルーのワゴンに乗って帰ることになった。
「おまえんちってテレビに映ったらヤバいんじゃねえの?」
などと家が近いので同乗している灰島が本気で懸念しているような顔で言った。
「うちをなんやと思ってんや。普通に堅気んちやぞ、堅気の」
陽が暮れた空には冬の星座がまたたき、山々に囲まれた紋代町の田園風景を小さな光が照らしている。のどかな景色の先に両端が闇に消え入るほど長々と東西に延びた漆喰の塀が見えてくると、「ん? あれ、家……?」と和やかだった車内の空気が怪しくなった。
ほどなくして、北斗七星を戴く北の山を背負って南側にどんと開かれた切妻屋根の門構えをヘッドライトが照らしだした。
「黒羽くんの家って、なにをやってるお家柄……?」
黒羽に向けられる口調が変な感じに丁寧になった。
「土地持ってること以外おれもあんまりちゃんと知らんのですけど……あ、ときどき議員の人とか来ます。なんか菓子折持って」
門前にワゴンがつけると、白砂利が敷かれただだっ広い前庭の先に構える本宅の玄関の前で祖父が出迎えていた。ロマンスグレーの頭髪をオールバックにし、着流しに羽織をはおって屹立している厳めしい体躯の祖父の姿がカメラに映る頃には、テレビクルーは蒼ざめた顔ですっかり尻込みしていたのだった。
「……なあ。放送できるのか?」
灰島が半眼で呟いた。黒羽も自信がなくなってきた。