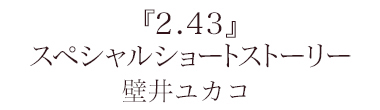暁~daybreak~
「ボール出し、やりましょうか」
遠慮がちにかけられた声に驚いて振り返ると、体育館の鉄扉の陰から棺野秋人が顔を覗かせていた。盗み見してるのもいたたまらなくなって声をかけましたとその顔に書いてある。ボールも持たずにネットの前でスパイクジャンプやブロックジャンプをしてみては、顔面をネットにめりこませて「あー」「無理やー」「昨日すごかったなぁー」と嘆くところを見られていたと思ったら、末森荊はぎゃっと心の中で悲鳴をあげた。
「だ、男子、今日オフやないんか。なんでこんな早起きしてんの」
「はよ目ぇ覚めてもて……。起きたとき昨日のことぜんぜん実感なくて、夢やったんやないんかって一瞬慌ててもた」
「昨日あんだけの試合しといて、ひと晩でよう回復するもんやなあ」
昨日、十一月二十九日、『春高』こと『春の高校バレー』の福井県代表決定戦が行われた。男子決勝の清陰高校対福蜂工業高校は最終第五セットまでもつれにもつれて二時間半に及ぶ激戦になった。観客席で大勢の歓声に呑まれながら勝利の瞬間を迎えたときの、あの興奮が今も鮮明に残っている。昨日の試合後からずっと、荊の身体の奥でオレンジ色の火種がちりちりと震えていて、下手をするとすぐまた燃えあがろうとする。
早く目が覚めたのは荊も同じだった。じっとしていられず、まだ女子バレー部の練習もはじまらない朝一番の体育館で一人でネットを張って、息を切らせて跳んだりはねたりしていたのだ。
棺野がバスケットのゴールリングの真下を通ってコートの枠の内側に入ってきた。ふとネットの上端の白帯(はくたい)に視線をやったので、
「あっこれ、2.43で張ってもた。わたしが行くわけでもないのになあ」
なにも言われないうちから荊はつい言い訳がましく自分から言った。
二メートル四十三センチは男子の全国大会のネットの高さだ。県大会は三センチ低い二メートル四十で行われていた。自分たちの学校の男子バレー部が、とうとう“本物の”2.43に手をかけた――身体の奥にある火種が、風に煽られたみたいに一瞬まばゆく燃えた。
「末森さんも東京まで来てくれるんですか」
「あーうん。昨日の今日やのにもう回覧板入ってたわ。黒羽のボンボンとこの親戚に福井市で旅行会社やってる人いて、東京観光&応援バスツアーのプランあっという間に組んだらしくって……さすがっていうか呆れるっていうか。ほんで町民総出で東京繰りだす気みたい。町の年寄りばっかりやで、はしゃぎすぎてなんか起こらんかって心配やしね。わたしも一緒に行こうと思ってる」
「よかったです。連れてけることになって。……って、すいません偉そうに、別におれが連れてくわけやないし、ほやし末森さんは自分で行きたいほうの人やと思うし……」
嬉しそうな笑みをこぼしてから棺野が慌てたようにつけ加える。昨日の試合で堂々としたプレーで幾度となく応援席をわかせたあの選手が、同じ町で育って昔から知ってる、このおとなしい性格の男の子と本当に同一人物だったんだろうかと、なんだかむずむずした気持ちになる。
「……ほやね、そりゃ自分で行きたかったけど。ほやけどこんなことにならんかったら東京まで春高見に行こうなんて思いもせんかったし、棺野たちが頑張ったおかげで連れてってもらえることになったんは本当やもん」すこし照れて、「……嬉しいよ。ありがと」
「いえ、その、どういたしまして」棺野が赤面して俯いた。
ありがとうっていう言葉を素直に口にできた自分が不思議だ。去年の自分ではたぶん言えなかった。自分にできないことを為し得た棺野を、自分の中で認められなかったんじゃないかと思う。
「あれ? 棺野に末森、二人とも早ぇな」
朝っぱらから覇気に溢れた声とともに戸口に現れたのは男バレ主将の小田伸一郎だった。ジャージの上にベンチコートを着込み、エナメルバッグを袈裟懸けにして、もちろん部活以外のなにをしに来たんだっていう恰好だ。
「小田先輩まで……男バレ休みやないんですか」
「いや、はよ目ぇ覚めてもてな。じっとしてられんかったし、誰もえんうちにちょっと練習させてもらおうと」
この人も同類かと呆れる荊の傍らで棺野が半眼で「いい感じやったとこに……」などと毒づいてから、しれっとした顔に戻って「おはようございます」と言った。
「誰がいるんかと思えば、棺野と末森さんか」
小柄な小田の頭の上からキリンが首を伸ばすみたいにして副主将の青木操まで顔をだした。「邪魔してもたな」と青木のほうはにやりと笑って棺野に片目をつぶってみせた。
「なんやぁ、おれらが一番乗りやと思ったら副主将……と、主将たちもいるげ」
続いて大隈、内村、外尾という二年組がぞろぞろと現れた。「なんやはこっちのセリフじゃ。今日はオフやっちゅうたやろ」「ほーゆう主将も来てるげ」大隈に突っ込まれて小田が渋面で口ごもった。
一月の春高本大会までたった一ヶ月余りだ。みんな練習したくてうずうずしているのが伝わってくる。荊の中の、手が届かない目的地を遠目に眺めてくすぶっているだけの火種は、彼らの中では明確な目的地を示している。
羨ましくないと言えば、やっぱり嘘になるから、
「もう、そもそも今朝は女バレの枠なんやで、男バレが集まってきたらわたしの練習にならんやろ! 男バレは解散ー!」
気持ちの発散ついでに荊は両手を振りまわして喚いた。
「ちゃんと休んでる一年生を見習わんか! 二、三年が手本にならんでどうすんや」
「あ、すいません。一年来てます」
と、そこへ面目なさそうに自己申告する声があった。
駐在所に出頭する容疑者みたいにぺこぺこしながら黒羽祐仁が姿を見せたのに続き、黒羽にベンチコートを引っ張られて灰島公誓まで現れると「灰島!?」と全員が目を剥いた。
昨日の試合終了と同時にぶっ倒れ、表彰式にも出席できず自宅に搬送された張本人だ。
「おれは休む気満々やったんですけど、なんとなくこいつ疑わしかったんで家まで見に行ったら案の定っちゅうか、朝から行こうとしてたんでー」
自分だけ無罪を主張する黒羽を灰島が横目で睨む。顔色を見るにまだ完全に回復したとは言いがたい。試合のときと違って細いフレームの眼鏡をかけた姿はひょろりとした文系少年といった印象だ。
「軽くボールにさわるくらい別にいいじゃないですか」
訛りのない標準語で灰島がぼやき、荊に視線を向けた。
「おれがトスあげましょうか」
「え!?」
え、に濁点がついたような声がでたので灰島が顔をしかめた。
「おれじゃ不足ですか」
「ふ、不足のわけないけどっ……」
壁際に持ってきていた女子バレー部のボール籠を引いて灰島がコートに入ってきた。ベンチコートを脱いで籠の縁に引っかけ、ボールを一つ手にする。青と黄色の配色が映えるミカサ製のバレーボールを片手で一回転させた、その瞬間、憔悴気味に見えた顔があきらかに変わった。空っぽの身体の中心にバレーボールという心臓が宿ったかのように、どこかふわふわしていた表情に魂が戻ってきた。
「ちょ、待って待って、打てんって。これ2.43で張ってるんやよ? やるんやったら女子の高さに下げ……」
「打てますよ、女子でも。スパイカーですよね、末森さん」
言い切られて二の句を失った。
女子のネットの高さは県大会で二メートル二十だ。二メートル四十三のネットに向かって打つ感覚は、たとえ向こう側が透けて見える網であろうが、不透明なコンクリートの壁が目の前にそびえているのと変わらない。
「末森さん、打ってみれば? 女子の練習時間なんやで遠慮せんと」
固まっている荊の背中を押すように棺野がそう言ってネットの前を灰島に譲った。男子優勝チームに見られていると思うと緊張しつつ荊がアタックライン付近まで後ずさると、
「もっと。一番高く跳べる助走取って」
灰島に言われてバックステップで大きく六メートル、エンドラインまで下がった。
「タッパと最高到達点言ってください」
「一七三センチ。最高到達点は……二八五」中学時代のほうが二九〇近く跳べていたと思うと語尾が澱んだ。「十分です」と灰島が答え、顎をあげて白帯の上方を見やった。目には見えないその“点”に的を置くみたいに一秒間だけ視線を据え、こちらに目を戻して、
「そっちの好きなタイミングで入っていいです。一番高いとこで打つことだけ考えて、思い切り跳んでください。こっちであわせます」
「好きなタイミングって、いきなり言われても逆に困るわ」
文句を言うと、灰島がちょっと興が削がれた顔で小首をかしげた。
「……じゃ、おれが最初、一回上にあげるんで」手首のスナップを効かせてボールを自分の直上に軽く投げあげ、「そしたら助走入ってください。おれのほうはもう見ないでいいです」無雑作に投げただけなのに、灰島自身は一センチすら動くことなく、おでこの前でオーバーハンド・パスの構えをした両手の真ん中にぴたりとボールがとまった。
「う、うん」一応頷いたが、いつも練習してるセッターとぜんぜんやり方が違って戸惑う。
「じゃあいきます」
と灰島が言うなり躊躇なくボールを投げあげた。
「ちょちょちょっと待って、早い早いっ」
慌てて助走に入ろうとしたがつま先が床に引っかかってコケそうになった。灰島が怪訝そうにいったんボールを片手でキャッチした。
なんか変な汗が一気にでてきた。
「末森先輩。大丈夫です」
と、一年生の黒羽から助け船がだされた。
「こいつは“信用できる天才”です」
灰島の顔を指さして、でも面白がって言っているふうでもなく、ごく真顔で。
肩を一度上下させて身体の力をリセットする。目で合図を送ると灰島が小さく頷き、あらためてボールを直上に投げあげた。荊は前方にそびえ立つネットに向かってバックアタックの助走のようなつもりで走りだした。
キキュッ。最後の二歩で踏み切る瞬間の、自分の真下で鳴る小気味よい音が好きだ。モップがけした体育館の床と、日々の自分の手汗が染み込んだシューズの底が擦れあう音。
一番高いとこで打つことだけ考えて。
思い切り跳んでください。
スイングの頂点に、まるで最初からそこに浮かんで待っていたみたいに、ボールが
二メートル四十三のネットが気にならなかった。まだ余裕があるくらいの高さで打ち込んだボールが向こうのコートの真ん中で跳ねあがった。ネットに突っ込みそうになりながらつま先でブレーキをかけて着地した瞬間「なに、今の!?」という声が思わず飛びだした。
こんなセットを、棺野たちは毎日打ってるんだ……そりゃあ気持ちいいよ……!!
「も、もう一本あげて!」
と興奮して灰島を振り返ったが、「末森。すまんけど」と小田の声に制された。
「あ……。すいません」
今日は休ませなきゃいけない、男子バレー部の大切なセッターだ。「一本も二本も十本も二十本も変わらないですよ」灰島本人のほうが不服を唱えたが、小田に無言で首を振られ、鼻白んだふうにボール籠に伸ばした手を引っ込めた。
「度胸ありますね、末森さん。一発で一番高いとこに飛び込んできてくれる人はあんまりいないです」
自分がすごいことをしたわけじゃないという顔で灰島が言った。それから、
「……ありがとうございます。信用してくれて」
ほっとしたように短い息をつくと、小さな笑みが口の端に乗った。
セッターを信用してスパイクに入るということが、スパイカーにとって口で言うほど簡単ではないと荊は知っている。でも、ここにいる彼らは――まわりでちょっとにやにやしている他の部員たちの顔を見まわした。ここにいる彼らは、このつっけんどんな標準語で話す、どうにもディスコミュニケーション気味な、けれどバレーの才能に限っては天下一品の、この一年生セッターを全員で信用すると決めて代表戦に臨んだのだ。そしてこの一年生は全身全霊をもってそれに応え、東京への道を繋いでみせた。
心は未だ昨日の熱戦に掴まれている。あの福蜂工業との試合以上にすごい試合なんて今は想像できなかった。でも考えてみれば昨日だって、始まる前の想像を軽々と超えたものを見せられたのだ。
清陰高校男子バレー部、一ヶ月後の春高で、きっとなにかもっと“すごいこと”を起こす予感がする。
――結論を言えば、応援ツアーへの荊の参加は叶わなかった。
思わぬ形で彼らの東京遠征に同行することになるとは、この時点で荊はまだ、というか