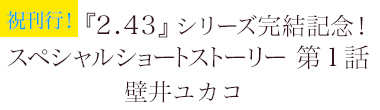高志寮の化け猫秘話
新学期のある晩、
「なんか今年豪勢やな? おれが入った年なんか肉は瞬殺やったで、ちょっと出遅れたらもう野菜しか食えんかったぞ。なんで今年は奮発してくれたんやろ」
上京三年目になる三村が恨み節まじりに不思議がっていた。三村の入寮当初といえばまだ松葉杖だったはずだ。肉の争奪戦に加わるのは厳しかったろうことは灰島にも想像できた。
今年一年生の灰島は過去のことは知らないが、約三十名の男子大学生の旺盛な食欲に耐えきるに十分な量の肉が今年は用意されている。開始三十分ほどたっているがまだ品切れになる気配はない。
「うちから届いたんですよ。寮に挨拶がわりにって」と黒羽が三村の疑問の種明かしをした。「清陰の合宿んときも毎回こーやったんで」
クール便で寮に大量の食材が届けられたのは今朝のことである。黒羽は「やりすぎんでくれって釘刺しといたら常識的な量でよかったわー」と胸を撫で下ろしていたが、でかいスチロール箱にぎゅうぎゅう詰めで届いた数十キログラムの
まあ黒羽家の差し入れを遠慮したところで、あの家の人々ががっかりこそすれよろこぶわけがないことは確かなので遠慮なく金串に刺された牛肉を頬張った。バーベキューグリルから運ばれてくる煙で眼鏡が曇る。
ほとんどの寮生は缶ビールを飲んでいるが、灰島と黒羽の手にあるのは紙コップに注いだウーロン茶だ。三村はもう飲酒ができる歳だが同じくウーロン茶に口をつけている。考えてみるとこの人が飲んでいるところをまだ見たことがない。
眼鏡の曇りが晴れたとき、バーベキューグリルのそばで妙な動きをしている者たちがいるのに気づいた。大口でかぶりついた肉を金串から引き抜きながら灰島は眉をひそめた。
「あひょほ、あひおそおそひへんら(あそこ、なにこそこそしてんだ)」
三人の寮生が小声で囁きあいながら、炭を足している寮監社長の目を盗んで紙皿に料理を確保している。「社長」と「おかみさん」と寮生から呼ばれている寮監夫妻は福井の出身だそうだ。寮の食堂では福井の料理もよく提供され、味噌汁も福井の味だ。
三人のうち二人が紙皿を隠し持って屋内への出入り口へ消えていった。部屋に持ち帰る必要は別にないはずだが。寮生たちはバーベキューグリルの周囲でみんなでわいわいやりながら飲食している。
「野良猫でもこっそり拾ってきたんかな」
黒羽がピンときた顔で言った。言われてみれば部屋に匿っている生き物に食べ物を持っていくような行動だ。笑顔も見せながら互いにつつきあってこそこそする様子には、バレるスリルと世話のよろこびを同時に楽しんでいるような雰囲気があった。
「ほんとに猫いるんやったらあとで見にいってみるけ?」
黒羽が声をはずませたが、ウーロン茶に口をつけながら三村が曰く、
「野良猫なあー。野良猫ってビールも飲むんか?」
三村が目配せした先で、三人の残りの一人が缶ビールを一本こっそり懐に忍ばせるのが見えた。三村にはなにか心当たりがあるようだ。やれやれというように苦笑して、足早に屋上から姿を消す寮生を見送っている。
「ほんなら誰かヒトが部屋にいるんですかね? 遊びに来るくらいはいいやろけど、寮の飯に堂々とありつくわけにいかんですしね」
住人以外の人間の立ち入りを禁じられてはいないので良識の範囲内で友人等を呼んでも問題はない。保護者が子どもの寮生活の見学がてら泊まっていくこともあるようだ。ただ食費は寮費に含まれるので食事の提供はさすがにない。このバーベキューも(おおかた黒羽家の差し入れとはいえ)寮費でまかなわれている。
「んーまあ、野良猫っていえば野良猫みたいなもんって言えんこともねぇかもな」
「はあ? どっちなんすか。意地悪せんと教えてくださいよ」
煙に巻くような言い方に黒羽が口を尖らせたが、三村はにやりとしただけで答えを教えてくれなかった。
「ま、住んでりゃそのうち遭遇するやろ」
*
三村とその“幽霊部員”とのファーストコンタクトは大学一年目の終わりかけのことだった。
「失礼しまー……って、えん(いない)のか」
星名監督に呼ばれて部室に来たが、無人の部室を見まわして三村は途方に暮れた。機材や書類も多く置いてあるのに不用心にも鍵はかかっていなかった。すぐ戻るということだろうと解釈し、そのまま待つことにした。
中央のスペースを占める机にだされていたパイプ椅子に何気なく腰をおろしたとき、
「――おわっ」
思わず声をあげてのけぞった。脚のあいだから生首がにゅっと突きだしてきたのだから勘弁してほしい。椅子ごとひっくり返りそうになったが部室の荷物の多さが幸いし、空を掻いた手が積んであった段ボールにぎりぎり届いた。
傾いた椅子に尻を乗せたまま声を失って生首を凝視する。
「んー。一瞬寝てた」
とか寝ぼけ眼で言いながら生首が机の下から這いだしてくると、まあ当たり前だが首の下には胴体がちゃんと繋がっていた。
「それ、おれの椅子なんだよね」
と指摘されて三村は「ああ……すんません」と椅子からどいた。同学年なのか先輩なのかもわからないので口調に困る。部室にいるからバレー部員なのか? それすらわからない。初めて見る顔だ。
面食らっている三村にかまわずその部員(一応部員だと思っておく)は椅子の上に足をあげてあぐらを組んだ。足も二本ちゃんとあるし、机の下に脱いだシューズが散らかっていた。机の上にはノートパソコンが開きっぱなしで置いてあった。
「もうちょっとで終わるから待っててね。練習のビデオからきみのスパイクのところ切りだして集めてるから」
パソコンを操作しながらその部員が言う。両手の指がキーボードの上をただ滑っているだけのような打鍵の速さに三村は驚きながら、
「えーと、おれのこと知ってんですか」
「タメだから敬語じゃなくていいよ」
「あ、一年なんか。っちゅうか誰や? 初めて会うよな? 会ってたらすまん」
傍らに突っ立っている三村にそいつが顔を向けた。パソコンから目を離してもタイピングは続いている。越智より速ぇんじゃねえか……。越智も高校の頃からブラインドタッチができたのでバレー部の仲間全員から「すげえ。神」と言われていたが、その越智より目の前のこいつのほうが速そうに見える。
そいつが笑うと両目が細まり、口角が三日月型に吊りあがった。
「アナリストだよ。まあ今週からだけど。よろしく、同志くん」
欅舎大バレー部の“幽霊部員”の話は聞いてはいた。スポーツ推薦で入ったほかの同期は三月初旬から練習に加わっていたが、三村は両膝の手術を受けたため約一ヶ月遅れで合流した。そいつは加入一ヶ月とたたず幽霊部員と化したらしいので、ちょうど三村とすれ違いになっていたのである。
幽霊部員になってほぼ丸一年後。そいつが突然舞い戻ってきた。
それが
「スロットにハマっちゃってさー。パチ屋に入り浸って部活行かなくなっちゃったんだよね」
と、あきれるしかないことを染谷は悪びれたふうもなく打ちあけた。
「パチスロで負けて懲りて出戻ってきたってことか」
「ん? 負けたとは言ってないっしょ。けっこう稼いでたよ」
「ほーなんか? ああいうんって勝てんようにできてんのかと思ってたわ」
「もちろん単発では負ける日もあるけど、長い目で見て黒字にする方法ってのはあるんだよ。スロットで稼ぐ方法って結局地道な作業なわけ。勝てる店と台を長期スパンで観察することと、膨大なデータ収集とデータの分析。したら高設定の台ってかなり見えるんだよ。ね、バレーも一緒っしょ?」
「一緒か……? おれにはぜんぜん共通点わからんけど」
「だから性にあっててハマっちゃったんだよねー」
「よう堂々と言うな……」
当時の三村にはまったく共感できなかったが、あとになって染谷の仕事を知れば膨大な数字の積み重ねと地道に向きあうアナリストとの共通点はあるのかもしれない……と、思わなくないこともないがやっぱりただの
「でまあ、これは星名さんと話つけた“
と、ウインクなんかしてみせて染谷が目配せしたノートパソコンの画面ではいくつかのウインドウがポップアップし、時間の進行を示すバーとともに映像が流れている。映っているのは見慣れた欅舎大の体育館に張ったバレーネットと、練習着姿の三村自身――練習中に録ったビデオだった。
部室棟の消灯時間が近かったので部室で全部見るのは無理そうだった。腰を据えて見れる場所ある?と染谷が言うので、三鷹の寮に染谷を連れて帰ってきた。
ベッドの上に置いた染谷のノートパソコンを前に、染谷と並んで床に座っている。
「きみが映ってる映像の中からスパイク前後の部分を切りだしたのがこれね」
スパイク時の助走、踏み切り、ボールインパクト、着地までの三村の映像が大量に集められている。部員全員の練習を記録しているビデオからこれらを集めるには相当長時間の映像を確認しないといけないはずだ。簡単な作業だとは思えなかった。部室の床で寝ていたことを思えば何時間パソコンに向かっていたんだろう……刑事ドラマなんかで何日分もの防犯カメラの映像に刑事が徹夜で目を通しているようなシーンがあるが、あんな仕事を思い浮かべるだけで三村は目がしょぼついてくる。
膨大なデータ収集……か。
「こういうんもアナリストの仕事なんか……。へえ……」
アナリストになると言って一浪し、近々二度目の大学受験に臨もうとしている親しい人間の顔が自然と頭に浮かんでいた。
「いい打点でしっかり打てたときと、打点が下がったときとで分類もしたよ」
「分類?」映像を集める作業だけで想像のぎりぎり限界なので分類となるともう三村の想像を超える。「そんな作業ようやるなあ。めんどくさくねぇんか?」
「それをやるのがアナリストだからね」
褒められたものではない趣味を悪びれずに話し、褒められて然るべき仕事を偉ぶらずに話す、妙な奴だった。
「いいときの共通点。悪いときはなにが違うのか。助走なのか、踏み切りなのか、テイクバックなのか――探せばなにかあるよ。一緒に探そう。同志くん」
「ってさっきからその、同志くんっちゅうのはなんなんや」
「同志みたいなもんでしょ。最初の一年、チームの役に立てなかったって意味では」
「おれとそっちの境遇一緒にすんのはちょっと図々しくねぇか?」
手術とリハビリに一年間費やしていた自分をパチンコ屋に一年間入り浸っていた染谷と一緒にされたくないと思うのは、さすがに傲慢と責められることでもないだろう。
「図々しくなきゃ一年遊んでて出戻ってこられないっしょ」
しかし染谷はこたえたふうもない。
「まあこれからの働き次第だよね。星名さんとは話ついたけど、ほかのみんなに許されるかどうかは」
「
三村が口を挟むと、飄々としていた染谷が初めてきょとんとした顔を見せた。
「ん?」
「統。みんなそう呼ぶし。三村統」
と三村は自分の鼻先を指さして繰り返し、にんまり笑った。
妙な奴……。だが、悪い奴ではなさそうだ。
周回遅れで同期を追いかけねばならない自分にとって、並走してくれる心強い味方がひょんなタイミングで現れたように思った。
ひととき三村の顔を見つめていた染谷が同じようににんまりと笑みを返した。
「
自分自身のスパイクフォームをこんなに集中的に見る機会は今までなかった。高い打点を確保して打ち込めたときに比べ、ジャンプや打点が中途半端になったときはどこが悪かったのか――助走なのか、踏み切りなのか、テイクバックなのか、ボールヒットのタイミングなのか――自分の動作の一つ一つを見つめなおす。
いつしか目の渇きも忘れるくらい没頭して映像を見つめていた。
「斎、今のと一コ前のやつと、並べて再生することとかってでき……」
画面から目を離して隣を振り向いたところで三村は言葉を切った。
「って、いねえ」
そういえばトイレに行くと言って立ちあがった気配に生返事だけした覚えがある。一人部屋だが水回りは共用の寮なので男子便所は廊下にある。
「遅ぇな……?」
しかしでていってからかなり時間が経っている。
部屋のドアから廊下に首を突きだして左右を見まわす。別に迷子になるような廊下ではない。一本道の廊下に各部屋のドアが並び、階段へと折れているだけだ。
男子便所に行く途中のとある部屋のドアが半開きになっていた。猥雑な話し声にまぎれて麻雀の牌を転がす音が漏れ聞こえている。
まさかな……と三村は顔を引きつらせて裸足のまま廊下にでた。
ドアの隙間からその部屋を覗くと、あたって欲しくはなかったが残念ながら予想に違わず、コタツの上にだした麻雀の卓を囲んだ寮生たちに染谷がしれっとまざっていた。
「斎ー……。今日はおれにつきあいに来たんやろ」
まったく、信頼できるのやらできないのやら。
「ああ、統んとこに遊び来てたダチやったんか? こいつ誰やろなーとは思ってたんやけど。ちょうど卓のメンツ欠けてもたとこやったで誘ったら二つ返事で入ってくれたんやって。統のダチにしてはなんか毛色が違う奴やなあ」
「誰だか知らん奴素性も聞かんと部屋に入れんほうがいいですよ、先輩……」吞気なことを言う先輩寮生に三村は半眼で忠告する。
慣れた手つきで牌をつまんだ染谷がたいして悪びれずにごまかし笑いをした。両眼が細まり、口角が三日月型に吊りあがる笑い顔は、人語を解する化け猫が笑ったところを思わせた。
「ありゃ、見つかっちゃったかー。一瞬まざってただけ、一瞬」