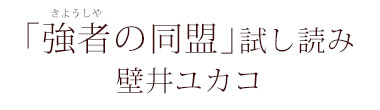「強者の同盟」試し読み 壁井ユカコ
「潤五(じゅんご)。ちょっと話したいことあるで、昼にでも来てくれんか」
監督の畑(はた)に呼ばれたのはクレープ屋に行った日曜の三日後、入学式も始業式も終わって新学期が本格的に滑りだした水曜だった。畑は福蜂工業の教員であり、男子バレー部の監督に就いて七年目になる四十歳手前の男で、二十数年前に自身も福蜂の選手として全国大会出場経験がある。
昼休み、部員が自主的にやっている昼練をパスして職員室を訪ねると、畑は高杉を連れて自分の担当教科の準備室に移動した。
「座っていいぞ」
と言われ、あいていた椅子を畑のデスクの脇に引いてきて座った。畑が自分の椅子を横にまわして高杉と向かいあった。
「おまえをセンターにコンバートさせようと思ってる」
咳払いを一つして畑がそう切りだした。
わざわざ二人きりになれる場所に移動した時点で楽しい話ではないんだろうと察して構えていたから、高杉は大きなリアクションはしなかった。
高校バレーのエースポジションといえばレフト(ウイングスパイカー)だ。バレーの試合で前衛のサイドや後衛のど真ん中から一番派手にスパイクを打っている選手がだいたいウイングスパイカーだと思ってもらえばいい。いわゆる点取り屋だ。高杉も中学時代ずっとウイングスパイカーとしてチームのエースを張っていた。しかし福蜂に入ってからは、公式戦でウイングスパイカーとしてコートに送り込まれたことはまだ一度もない。
センター(ミドルブロッカー)は敵のスパイクを防御するブロッカーの要となるポジションで、攻撃においては主にネット際で速攻(クイック)を打つスパイカーである。サイドから打つウイングスパイカーの囮としての役割も大きい。
ウイングスパイカーと同様に長身の選手が担い、ネット際で跳ぶ回数はウイングスパイカーと変わらなくとも、ウイングスパイカーが見た目に派手な得点を重ねていく陰で、ミドルブロッカーは多くは直接的にはスコアブックに現れない働きをしている。ミドルブロッカーをエースにしているチームもないことはないし、速攻が有効に機能することがウイングスパイカーの決定率にも掛かってくるのだから戦術上その役割は極めて重要だ。しかし表向きにはやはり地味なポジションであることは否めない。選手の性格的にも真面目で献身的にチーム全体のために働ける選手が向いていると一般的に言われている。
高杉と同じ二年のウイングスパイカーには、そのポジションを外されることなどまずあり得ない絶対的エース――三村統(すばる)がいる。
「今はまだ三年に統のまわりを固めてもらってるけど、二年中心のチーム作りもこれから見据えてかんとあかん。それにあたっておまえにはセンターを任したい。他にも何人かポジション替え考えてるけど、おまえもそのつもりでいてくれ」
自分に拒否権はあるんだろうか? 畑は決して甘くはないものの独裁的な監督ではないから、選手の希望を聞き入れて考えなおしてくれるかもしれない。そんなことも頭をよぎった。
しかし一拍沈黙したあと高杉は「……わかりました」と答えた。
大柄な身体を椅子に押し込んだ畑が腕組みをし、薄いリアクションの裏側の本心を読み取ろうとするように高杉の目を見つめてくる。高杉は畑の目を見つめ返した。目を逸らしたら、不満があると思われそうだから。
「……潤五。おまえは中学でずっとエースをやってきたな」
「はい」
畑は県内の中学の大会にも足を運んでいる。福蜂は公立高校だから推薦枠があるわけではないし、直接的に選手を引き抜いたりといったことはできないが、有望な中学生には気さくに話しかけてくれ、アドバイスもくれる。高杉は中学のバレー部の顧問を通じて畑から福蜂に来ないかと声をかけてもらった。三年の夏の決勝で三村の進英中に負けたあとにも話しかけてくれた。とにかく目立つ三村だけでなく、高杉のことも畑はちゃんと見ていてくれたんだと嬉しかった。
「今さらおまえに言う必要もないことやろけど、センターはエースやない」
ずきんと心臓が痛んだ。目の奥が一瞬熱くなった。表情に表れないように奥歯に力を入れた。
中学での高杉の活躍を知っていながら、残酷な宣告をするんだな……。膝の上で静かに拳を握りしめた。
「センターはチームの壁や。味方の攻撃を通すための銃眼や。チームを守る楯や。おまえに、それになって欲しい」
*
ネットの上から鋭い角度で打ち込まれたスパイクが床板をぶち破りそうな音を立てて対面コートに突き刺さった。ボールが急回転しながら跳ねあがり、対面コートに入っていたレシーバーがあんなもんは受けたくないという顔でボールを追って頭上を仰いだ。
「も一本来い!」
今スパイクを打った三村が凄みのある声で三年のセッターに指示した。バックステップでコート後方まで下がりながら、右手の人差し指を立てる。セッターにだしてもらうトスのサインなのだが、高く掲げた指先が、チームの〝一番〟を自ら表しているかのように高杉には見える。額に汗の玉が光っているが表情は力強く、〝1〟を要求する姿が堂に入っている。
タタッという軽やかな助走から、一転してドンッと両足で強く床を踏みつけ、空中へと身体を跳ねあげた。たっけぇ……! 背丈はまだ高杉のほうがあるのに三村のほうが遥かに跳ぶ。空中で弓なりに反った長身瘦軀が寸秒、重力から解放されてふわっと滞空する。弓を引き絞るように引いた右腕がしなると同時に、手の先に向かってエネルギーが駆けのぼる。
空中に浮いたボールがエネルギーをぶち込まれ、何倍もの質量の塊になってネット上から撃ちだされた。今度はレシーバーが真正面で受けたものの、強くはじかれたボールが天井まで跳ねあがった。
と、ガコ……と軋む音が聞こえたきりなにも落ちてこなくなった。「おえーっ」とまわりの部員たちからどよめきがあがった。
身体をくの字に折って着地した三村が天井を仰ぎみて「うげっ、すんませんっ」とぎょっとするなり、背に纏ったマントのように尾を引いていた凄みのオーラが引っ込んだ。
青と黄色の配色が鮮やかなミカサのボールが天井の梁の隙間にちょうどよく嵌まり込んでいた。
「あーあ。ボール安ないんやぞ。知らんうちに一個ずつ減ってってるし」
「あれ取れるんけ?」
練習の緊張感がどこへやらみんなで上を見てやいやい言いはじめる。
「すんませんーおれのせいです。当てて落としまっす」
三村が別のボールを持ってきて真下で構えた。天井に視線を据えて一瞬鋭い顔つきになり、ネコタジキデン、とかいう謎の呪文を唱えて、アンダーハンドで高いサーブを打った。
「あほかー。天井サーブで当たるわけが――」野次りながらみんなが仰ぎみた先で、見事、天井に嵌まったボールにサーブが命中した。「おっナイス、統」「まじか。すげぇ」と賞賛の声があがったものの――。
一球目を奥に押し込んだあげく二球目も嵌まり込んだ。
「おお。奇跡」
目を輝かせて自画自賛した三村を「二次災害起きただけやろがっ」といっせいに三年がどついた。
「もいっぺんチャレンジ」
「やめろ統。おまえはもう手ぇだすなや」
「むしろ三つ目嵌めたなってきてるやろおまえ」
妙に意欲満々でもう一本天井サーブを打とうとしてボールを奪い取られる三村には、あの恐るべき威力のスパイクを打つときの凄みはすでに微塵もない。ただの部内のひょうきん者だ。
こんな奴が……と、どうしてもときどき思う。こんな奴なのに……。
どの部員が打つよりも、三村が打つスパイクは音が重い。全身をバネにしてボールを撃ちだすエネルギーに変えてくる。"違い"を思い知らされる。中学時代に対戦していたときよりも、同じチームになって間近で毎日見るようになってからのほうが、ボディブローを毎日打ち込まれるかのように身に刻まれる。
〝三村のチーム〟としてこれからの福蜂は強固になっていくのだろうと、否応なしに納得させられる。
そのときに、自分のポジションは――コートの中のポジションであり、そしてチームの中のポジションは――どこにあるんだろう?
「おれ、上から当てて落としてみます」
わいわいやっている輪に入れないまま高杉はきびすを返して壁際の梯子に向かった。二階の高さの壁に沿って手すりつきのギャラリー(通路)がぐるりと造られている。ボールを二つばかり片手に抱え、梯子を使ってギャラリーの上に登った。真下からよりも横方向から当てたほうが落とせるんじゃないかという思惑だ。
……ネコタジキデン、って猫田直伝かよ(天井サーブの発明者だ。直伝のわけねえし。昔の人だ)。今さら気づいてあほらしくなっていたら、
「潤五、おれがやるで練習戻れや」
と、越智(おち)が高杉のあとから梯子を登ってきた。短パンやハーフパンツに膝サポーターといった練習着姿の部員たちの中で一人だけ長ズボンのジャージを穿いている越智は男子マネージャーだ。越智が上から指示し、一年の部員がボール籠をギャラリーの真下に押してくる。
「ほんなら任すわ」
持っていたボールを越智に投げ渡そうとして、ふと思いなおし、手が届く距離まで近づいて手渡した。
「先生から聞いてるんやろ」
ボールを受け取りながら越智が高杉の顔を見あげた。一瞬きょとんとしたがすぐ察したようで、「……ああ。ポジション替えの話な」と軽く目を伏せて頷いた。
畑と話した日からまた三日たち、土曜の今日は朝からどっぷり練習漬けだ。越智は畑の信頼も篤い。ポジション替えを告げた部員の様子を畑から訊かれていても不思議はない。そして越智が聞いたということは、
「統に話したんけ」
「ん、ああ。ちらっとだけな」
「なんか言ってたけ、統」
「いや……特には」
ふうん、と相づちを打って越智の手にもう一つのボールを押しつけ、二人がぎりぎり並んで通れる幅のギャラリーをすれ違った。
「……潤五。勝つためやぞ。統になんか思うんはやめろや」
越智の声が背中にかかった。生真面目に諭す声には、同情と共感がいくらか含まれていた。今では三村の女房役でありチームの裏方として献身する越智も、一年時には高杉たちと同じく選手として入部した。しかし伸び悩み、怪我もあってマネージャーに転向したクチだ。
「……統の態度次第やな」
それだけ言って高杉は梯子をおりはじめた。ちょうど下の扉から畑が入ってきたところで、気づいた部員から順に挨拶があがった。
越智には感づかれてるんだろう――他の連中がみんなそうであるほどには、高杉は三村を好きじゃない。
自分たちの代やその下の代は、三村率いる進英中の無敗伝説を知って福蜂に入ってきている。一年の戸倉なんかは特に三村への憧れが強く、弟子を名乗りかねない勢いでその背中を追いかけている。三村のプレーを真似し、三村からなんでも吸収しようとすることに躊躇がない。
だが、高杉には素直にそれができない。
戸倉のように一つでも歳が下だったらなにも考えず純粋に目標にし得ただろうし、一つでも上だったら、まあたぶんかわいがっただろうと思う。
〝絶対に勝てない奴〟と同じ学年に生まれたっていう、自分ではどうにもできないことが、バレーをはじめたそのときから、そしてバレーを続けている限りこの先もずっと自分の人生にはつきまとい続けるのだ。
「今日の残りは一年も入れて紅白戦をやる」
部員を集めて畑が言った。
一年が入った現在の部員数は三学年で総勢二十名ちょっとになる。交代要員込みで三チーム作ってちょうどいい人数だ。コートに入る二チーム以外の一チームが審判や線審につき、順番にゲームをまわしていく。
「ほんで早めに切りあげて花見行くぞ。今日くらいに行っとかんと、足羽(あすわ)川の桜もそろそろ終わってまうでな。ジュース代くらいはおれの財布からだしてやるで。そのかわりおれに一本だけビール飲む許可をくれ」
強面で下手なウインクなんかしてみせる畑に部員一同から歓声が起こった。畑もまんざらでもないノリで手をあげて応えたあと歓声を静めるジェスチャーをし、
「今やったら屋台もでてるやろ。今日の勝ち点一位チームには一人一品食いもん買ってやる。残り時間集中して腹すかせろや」
「監督まじで? 屋台にあるもんなんでもいい? クレープとかチョコバナナとかでもいい?」
一番前にいた三村が真っ先に餌に食いついた。おまえ一週間前にクレープ食ったばっかなのにまだ食いたいのか……。全員の頭の上から三村が半身がでるほど跳びはねるのを一番後方で見やりながら高杉はげんなりする。半年に一度くらいは食ってもいい気分になるが実際食ったらあと三年は食わなくていいと思う、というのが高杉の中のクレープの位置づけだ。
「ほんなら一応出欠取るんで、行けん人は帰りまでにおれにひと言言ってきてください」
越智がてきぱきと事務能力を発揮する。花見といえば、中学の面子での花見も今日の夕方じゃなかったかとそのときになって高杉は思いだした。遅れるかもしれないが一応参加という言い方で寺川には返信しておいたが、今の今まで完全に意識から抜け落ちていた。
しかし越智に欠席を申しでている部員は今のところいないようだった。うちの部って全員仲良すぎじゃないのかとつくづく思う。本当に一人も他の予定とか約束とかないのか? なにもないとしてもせっかく早くあがれるなら帰って寝たいと思う奴くらいいてもいいのに。
日曜の赤緒との別れ際を思い返すとどうにも気が重かった。赤緒の話だと今年は集まりが悪いらしいから、赤緒や寺川と膝を突きあわせてしっぽりした感じでディープな話なんかすることになるのかと思うとますます億劫になる。エースポジションからコンバートされるっていう話を赤緒が知ったら……。
〝負け組は梓には釣りあわん〟
……寺川には断りのメールを入れておこう。やっぱり部活で行けなくなったと言っても噓ではないし。
「一時半やな……ほんなら五時半までや」
畑がステージの上の壁を振り仰いだ。ボールよけの鉄の柵が嵌まった丸時計は一時三十分過ぎを示している。
「二年で一チーム、一・三年まぜて二チーム作る。三チーム総当たりで九セット。二セット先取しても三セット目もやる。ポジションとキャプテンはおれから指示するけど、ローテは任せるで各チームで作戦立ててやれ。リベロは抜きや。全員打て」
やや和らいでいた声色が再び厳しくなり、部員間にも緊張感が戻った。花見前の余興のような紅白戦になったとはいえ、残り四時間全部試合をやるというのはこれっぽっちも楽な練習ではない。
「二年チーム、キャプテンは統。ポジションはレフト」
当然のようにまず畑の口から三村の名前がでた。
「センターは壱成(いっせい)と、潤五」
こっちを振り返った者が何人かいた。若干驚いた顔を見せたのは朝松壱成一人で、他の連中はなにか深読みしたわけでもなさそうだったが。朝松は三村と同じ進英中でミドルブロッカーをやっていた奴だ。いわば三村とはずっと組んでいる。高杉がミドルブロッカーに転向するとなると今後は朝松とレギュラー争いをすることになる。
既成事実を作っておれを納得させるための今日の紅白戦、ってことか。二年中心のチームを見据えるにあたって新ポジションの感触を探ろうというまっとうな目的も無論あるんだろうが。
畑の意図は明白だったが、高杉はぴくりとも頰を動かさず「はい」と返事をした。
承知済みだっていう顔をするしかなかった。不満があるとか、傷ついてるとか、そんなことはいっさいないっていう顔を。自分の力では抗えない何者かがでかい手のひらで心臓を押しつけてくるような、今感じているこの胸苦しさをここにいる仲間に知られることだけは、最後の悪足搔きみたいなものだが、絶対に許せなかった。
どうしたって三村の反応が気になった。だが三村のほうは高杉の心中などべつだん気にしたふうもなく、
「監督。こっちのセッターに掛川(かけがわ)ください」
と、いつもどおりの調子で唐突に畑に申しでた。集団の端っこにいた掛川本人が「えぇ!?」と仰天した声をあげた。
他の部員からも意外そうな視線が向けられ、どっちかというとおとなしいタチの掛川が挙動不審気味に赤面した。わかりやすく羨ましそうな顔をしたのは戸倉だ。掛川も戸倉と同じ一年。もちろん入部したばかりだ。中学でもポジションはセッターだったことは高杉も知っているがどんなタイプのセッターだったのかまでは知らない。そんなにいい選手だったのかと驚いた。
「まあいいやろ。二年は越智も入れんとどうせ足りんしな。掛川は二年チーム入れ」
畑の了承を得て掛川が「は、はいっ」と意気込み、手招きしている三村のところへと顔を強張らせながらも嬉しそうに駆け寄った。
三村が軽く頭を下げて掛川と顔を突きあわせ、なにかひと言ふた言話したあと、
「よっしゃ。二年&掛川チーム集合ー」
と手をあげて他のメンバーにも号令をかけた。
「クレープとチョコバナナとシェイクのためにぃーっ、頼むぞおまえらぁ!!」
円陣を組ませてわけわからん活を入れるキャプテン三村に「一人一品やなかったか」「シェイク増えてるげ」と笑いまじりのツッコミが入りつつ、掛川を含めた全員、「おおっ」と声をあわせて円陣の中心に拳を集めた。
円陣の中で三村と目があったのは、高杉にとっては不意打ちだった。
高二の四月現在で高杉は一八八センチ。三村は一八〇センチ台半ばだろう。一年前に入部したときは十センチ以上の差があったはずだが、高校生になってからはもうほとんど伸びなくなった高杉と逆に三村は高校から伸びはじめた。そばに立って比べる機会があるたびに差を縮められている。それでもまだ今のところは高杉のほうが目線が上にある。それを意識するように高杉はあえてすこし顎をあげて三村の顔を見返した。
なにを考えてるんだこいつはと、不思議でしょうがない。越智からどこまで話を聞いてるんだ? 三村はたいていバカをやっているが何気にクレバーだ。高杉が三村に多少なりともわだかまりを抱いていることを察していないほど鈍感な奴じゃないはずだ。
なにか言えよと焦れると同時に、なにか言われることを恐れている。もしこいつの口から同情的なことなんかを言われたら……。
「……ほんならおれは焼きそば大盛り狙って勝ち行くわ」
繕ったものをぶち壊される前に自分から軽口でごまかし、視線を外した。
六人制バレーボールにはローテーションというルールがある。コート上の戦術に終始必ず絡んでくる、バレーという競技ならではの特徴だ。
前衛三人と後衛三人、それぞれ左からレフト、センター、ライト。この六箇所を、自チームがサイドアウトを取る(相手チームからサーブ権を奪うこと)ごとにプレーヤーが時計まわりにまわっていく。サーブが打たれてプレーがはじまったら移動は自由なので、各々の持ち場に素早く移動できるようサーブ直前の六人の位置取りの連携も重要だ。ただし後衛になっている三ローテのあいだは前衛でブロックに跳ぶこと、前衛からスパイクすることができない。
これにより前衛の攻撃力が落ちるローテーションや、三村のように本来レフトから打つのを得意とするウイングスパイカーがライトから打たねばならないといったローテーションが、どんなチームにもどこかしらで必ず発生する。チームにとっては「弱点のローテ」、つまり早く切り抜けてまわしたいローテになるのだが――。
「バックライッ、こぉい!」
やたらよく通る三村の声がコート後方から突き抜けた。自らレセプション(サーブレシーブ)した三村がバックアタックに飛び込んでくる。三村が後衛ライト、高杉が前衛ライトのローテーションだ。掛川がライト側から来たやや難しいパスを落ち着いたハンドリングでまたライト側に折り返した。ネット前で高杉が速攻に入っていたが、ボールはまるで三村の声に引き寄せられたみたいにネットから離れて高くあがった。
一・三年Aチームのブロッカーは囮で跳ぶだけになった高杉につられることなく、三村の前にしっかり三枚ついた。そりゃそうだ。おれがなんでおまえより早く跳んでるかちょっとは考えろと言いたくなるくらい三村がのべつまくなしに煩いのだ。囮の意味がない。
ふわりと綺麗にあがったトスを高い打点で三村の右手が捉える。だが三枚ブロックが待ち構えている。捕まるか――とフォローに入ろうとした刹那、バズーカから撃ちだされたロケット弾のごとき破壊力でもってスパイクが三枚ブロックの壁にひびを入れ、ばちぃんという音をさせて相手コートの後方まで吹っ飛んでいった。
「うっしゃあ!」
自コートの中を走りまわって得点をアピールするのも、煩い。
ゲームがはじまってからずっと声だしてるし、ずっと動いてる。途中でへばることなんか気にしてないみたいに。
三村がトスを呼ぶ声には圧力すらあった。自分が打つっていう執着といってもいい。わざわざ掛川をセッターにもらったのは、まだ一年で従順な掛川なら自分の言いなりにトスをよこすと考えてのことだったのかと勘ぐってしまう。
「掛川。統につられんと、おまえが状況見て誰に打たすか決めろ」
チーム分けを決めた以外はあれこれ言わずに部員たちのやり方に任せていた畑がさすがに口を挟むくらいだった。
「先輩ー。全部おれが打つでおれにブロックついとけばいいですよ」
が、三村は畑の苦言に反省の色を見せるどころかネットの向こうの三年を煽る始末だ。一・三年Aチームには三年のレギュラーのミドルブロッカーとウイングスパイカーがいる。いずれも身長は一九〇前後だ。現福蜂の最強の壁であり楯である。「おめぇ統、生意気じゃー。ほんならもしおまえ以外が打ったら花見で奢らすぞ」軽口半分、本気半分っぽい声に三村はからから笑って「いいっすよー」と請けあった。
今の得点で二年チームがサイドアウトを取り、ローテーションが一つまわる。後衛ライトに下がった高杉がサーブを打つ番だ。
「潤五。ジャンサ」
三村が投げてよこした声に高杉はすこし驚いて振り返った。「一本!」と屈託のない声援を受け、相手コート側から転がされてきたボールを拾ってエンドライン後方に立った。
ウイングスパイカーにジャンプサーバーが当然のように多いのに比べ、ミドルブロッカーにジャンプサーバーは実は少ない。海外の試合を見るとそうでもない印象なのだが、少なくとも高杉のまわりでは。しかし中学時代エースを担っていたからには高杉もジャンプサーブを持っている。言われてみればミドルブロッカーになったからといってもともと持っている武器を封印する理由はなにもない。
だったらせめてサーブは恰好つけてやろう。
攻撃時はネット前に詰めていることが多いミドルブロッカーでも、ジャンプサーブはウイングスパイカーの派手なスパイクと同じように好きな助走を取って打ち込むことができる。中学のときなんかは「ジャンサの前のカッコつけたルーチン」の研究を、海外の代表選手を真似たりしてサーブそのものの練習以上に熱心にやったものだ。
右手一本でボールを摑み、正面にまっすぐ突きだす。野球の予告ホームランっていう感じで、これが一番イカしてるという結論にたどり着いたのだ。
つと視線をあげると、結局まだ救出できていないミカサのボールが二つ(二つ目は二次災害のやつだ)、梁の上でなんだか気恥ずかしそうな顔を並べていた。
右手で逆回転をかけたトスを高く放りあげる。天井の小さな二つのボールに目の前のボールがかぶさって視界から消えた。助走を大きく取り、天井に一度吸い込まれて自由落下してくるボールを高い打点から打ち込んだ。よし、入った! 背筋にびりびりと快感が走るのを感じながらエンドラインを超えてコートの中に着地した。
コントロールは若干甘かった。相手チームのレシーバーの真正面。しかし威力のあるサーブがレシーバーをひっくり返らせ、ダイレクトでネットのこっち側に返ってきた。「チャンスボール!」相手に攻撃のチャンスをやることなく攻守が入れ替わる。ゆるく返ってきたボールの下に掛川が直接走り込んだ。
「バックライト!」
サーブの着地からそのまま助走に入りながら高杉は思わず鋭い声をあげ、自分自身にはっとした。
「真ん中ぁー!」
と、高杉の声を食うような大声で三村がトスを呼んでバックセンターから飛び込んできた。二人がバックアタックに入るという状況になり、前衛で速攻に跳んだ朝松にはつられなかったブロッカーが寸秒、次の動きに迷った。
掛川のトスはまた三村の声に引き寄せられるようにバックセンターにあがった。強い引力を感じ、高杉まで滞空中にふと隣を見ることになった。
自分の真横で三村の爆発的なスパイクが炸裂した。ノータッチだったらアウトだったかもしれないが、一瞬遅れて跳んだブロックの先に引っかかった。ブロックが触れてもボールは勢いを削がれず後方のギャラリーまで吹っ飛んでいき、バスケットのゴール板に激突した。
「っしゃ! ナイッサ潤五!」
「ああ……悪ぃ、ついバックアタック入ってもて……」
「このローテんときこの攻撃使えるんは強ぇな」
はたきつけられたロータッチに応じながら言いかけた高杉に三村が食い気味に声をかぶせてきた。
「次もチャンスあったらやろっせ」
と嬉しそうに言われ、高杉はなんとなく狐につままれたような心地で、「も一本!」という声に背中を押されてサービスゾーンに向かった。
三村は目立ちたがり屋だが、相手チームをふざけて煽ったり、味方のスパイカーを押しのけて自分が全部スパイクをもぎ取るようなワンマンな奴だっただろうかと、このゲームがはじまってから高杉はずっと違和感を抱いていた。たぶんチームの中で三村に一番好意的な目を持っていないのは自分だが、だからこそこいつを正当に評価する目だけは曇らせないようにしようと、たぶんチームの中で一番意識的に自戒しているのが自分でもある。ただの妬みにならないように……自分自身を貶めないように。
なに考えてるんだ、おまえ。なにか企んでるんだろ……?
全部自分が打つ宣言などというもので三枚ブロックを自ら引きつけておいて、いくら三村でも一人でブロッカー三人を相手にし続けられるわけがない。ワンタッチを取られて攻撃を切り返されるようになった。それでもシャットアウトを食らうことはまだ一度もないのは驚愕としか言いようがないが。
ローテーションが半周して高杉が前衛レフトにあがったところで、肩の後ろでこそっと掛川が言った。
「潤五先輩、次からあげます」
つい高杉はまばたきしてしまったが、相手コートにはリアクションを気づかれないよう何食わぬ顔でネットのほうを向いていた。
「レフト持ってこーーーい!」
三村が相変わらずやかましく自己主張してレフトにまわり込んでくる。ネット前でAクイックに跳んだ高杉に目の前のブロッカーが一瞬反応しかけたが、足を踏ん張るようにして跳ぶのをこらえ、サイドの三村を目で追った――と、その頭の真上に掛川のトスがあがり、高杉の右手にふわりと入った。まじでこっちかよ、とトスをもらった高杉自身が驚いた。
視界を遮るブロッカーの手のない状態で、ぎょっとしたまま動けなかったブロッカーの真後ろにボールを落とした。
「……ってこら、統ーーー!! 全部打つっつったやろげぇーーー!!」
相手チームのみならずコートの周囲で審判係についていた一・三年Bチームからも怒濤のブーイングがあがった。まあ当然の抗議だなと高杉も異論はない。これには越智まであきれ顔をしていた。
「なに言ってんですか、こんなもん駆け引きでしょ、駆け引き」
三村は悪びれるどころか策が嵌まってさも愉快そうににやにやしているという厚顔無恥っぷりである。
「噓はついてませんって」
「どの口が!?」
「約束どおり奢る気でやったんで。潤五と折半で奢ります」
「ちょっと待て、巻き込むなや!?」
しれっと共犯にされて高杉は目を剝いた。
「おまえら私語いい加減にせえや! 花見やめんするぞ!」
畑の怒声が飛んできて全員慌てて真面目な顔を繕って口をつぐんだ(花見のために)。
サイドアウトを一往復挟んでサーブ権を取り返し、こっちのローテがまた一つまわって掛川が前衛にあがる。このローテまでは三村と高杉がまだ前衛で並ぶ。セッターが前衛にいるときは前衛で打てるスパイカーが二枚になるため普通なら弱いローテになる。
「潤五。さっきのダブルバックアタックみたいなん、前衛でもやろっせ」
三村が顔を寄せて耳打ちしてきた。ネット前で両手を軽くあげて構えながら高杉は訝しんでその耳もとに囁き返した。
「時間差でなくてか?」
「次から潤五にもブロックついてくるやろ。ほやけどウイングと同じ助走で跳べば潤五やったらブロックの上から打てる。ブロック打ち抜くスパイカーが前衛に二人いるんは向こうの守備にとって単純に脅威や。おれと潤五が前衛んときが、一番強いローテになる」
ネットのほうを見据えて不敵な顔で三村が言い切った――その台詞に、全身の産毛がざわっと逆立った。
掛川に無言で視線をやる。掛川が肩を竦めて小さく笑った。
「ここまでは統先輩が囮でした」
そういうことだったんだろう。あれだけコート中で動きまわって声だしまくってる奴が一番の囮じゃなくてなんなんだ。味方も引っ張られたが、むしろ相手チームにとって目にも耳にも三村の存在感は煩くてしょうがなかったはずだ。全ローテで三村の動きを意識せずにいられないのは相当なストレスだ。
本職はリベロだが今日はセッター対角に入っている猿渡(さわたり)のフローターサーブでプレーが再開した。前衛センターの高杉の右に前衛ライトの三村がいるローテだが、レフトから主砲を放つ三村が素早く高杉の背後をまわって左に動く。
二人とも同じレフトのウイングスパイカーだったらコート上では"対角"に入ることになる。対角はローテーション上で必ず前衛と後衛に分かれる。しかしウイングスパイカーとミドルブロッカーであれば、前衛で並ぶローテが発生する。"一番高いローテ"を三村と組めるのだ。
高さの利が生きるのは、言うまでもなく攻撃時だけではない。
猿渡のサーブがネットの上端に軽く引っかかり、相手コートのネット際に落ちた。「ネットイン!」コートの内外からわあっと声があがった。前衛ミドルブロッカーが危うく突っ込んで拾ったが、この時点でミドルブロッカーの速攻はなくなる。「統、ライト!」指をさして三村に指示を飛ばすと「あいよ!」と威勢のいい応答があった。ライトに開いたウイングスパイカーにトスがあがり、高杉と三村の二枚でブロックにつく。
掛川も決して劣ってはいないが、やはり三年の正セッターのトスは綺麗だ。スパイカーの全身全霊の力でブロックの上から叩き込む、福蜂のバレーのスタイルを思う存分発揮できる。
だが、ぴたりと呼吸をあわせて跳んだ二枚ブロックのど真ん中!――三村の右手と高杉の左手にほぼ同時にあたり、スパイカーの真下に叩き落とされた。
着地しながら雄叫びのような声が無意識に喉から飛びだした。左手に受けた無形の手応えを形にして摑まえるように、拳をぎゅっと握りしめた。
ネットの前で「っしゃあ!」とつい三村と声を揃えて固い握手を交わしてから、我に返って微妙に気まずくなった。
「勝つぞ、潤五」
と言われて「そりゃ……」とごまかすように軽く瞳を揺らして答えかけたとき、
「全国で勝つぞ」
いつも明朗すぎるほど明朗な三村の声がワントーン低く、重みを増した。まっすぐに見つめてくる三村のまなざしを受けて高杉は絶句した。
「おれたちの代でセンターコート行くぞ。……絶対に」
普段表にだしている三村の軽薄なキャラクターとは違い、その言葉の裏には切実に勝利を欲する必死さがあった。
自分や赤緒と、三村も同じなのだ――いや、自分や赤緒以上にでかい舞台で、今まで何度も負けてきた奴なんだ。三村だって決して〝一番〟ではない。
「頼むな」
痛いほどの力を一度入れてから三村から手を放した。
やはり越智から話は全部聞いていたのだろうと確信した。でも、こういうことで多くを語らない奴なんだな……。
高杉が予想していたどんな言葉も三村は口にしなかった。ポジション争いに負けた高杉に気を遣ったり、なにか遠慮するようなことを言ったり、あまつさえ謝ってきたりしたら、高杉の心にはどこかしら三村を認めたくない感情がずっと残ったかもしれなかった。
余計ななぐさめやフォローをするかわりに、ただ行動で、コートの中で説得してきた。
おれは"戦力"としてここに、このチームにいる。三村に負けたんじゃない。勝つために、こいつの隣にポジションがある。
三村は高杉を敗者にしなかった。だからこそ、
勝てねぇなあ、こういうところは……。
という素直な気持ちが、今はなんのつかえもなく、すとんと胸に落ちてきた。
この一年間、自分の中でこれ以上拡がらないように、水位があがらないようにと一人で必死に足搔いてきたどす黒いタール状の水溜まりに一滴の透明な雫が落ちて、王冠型の澄んだ波紋が広がっていった。
*物語の続きは『空への助走 福蜂工業高校運動部』でお読みください。