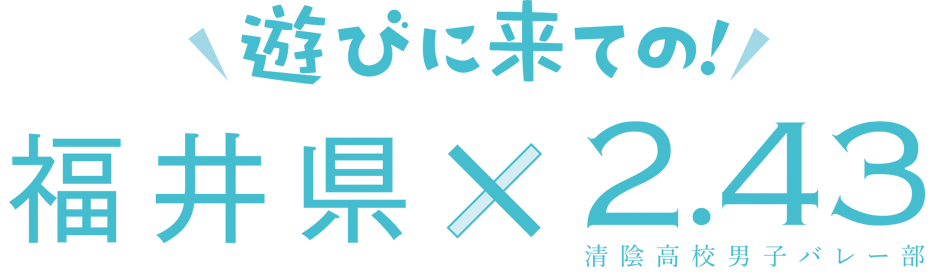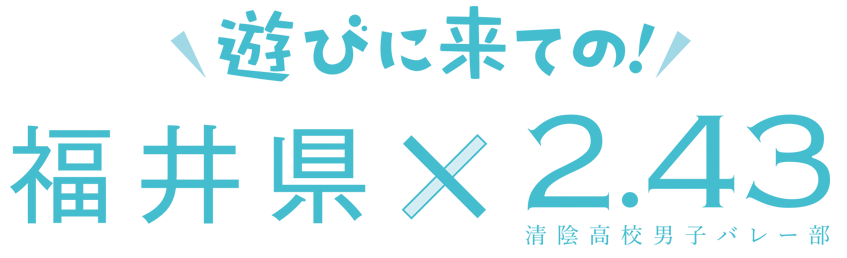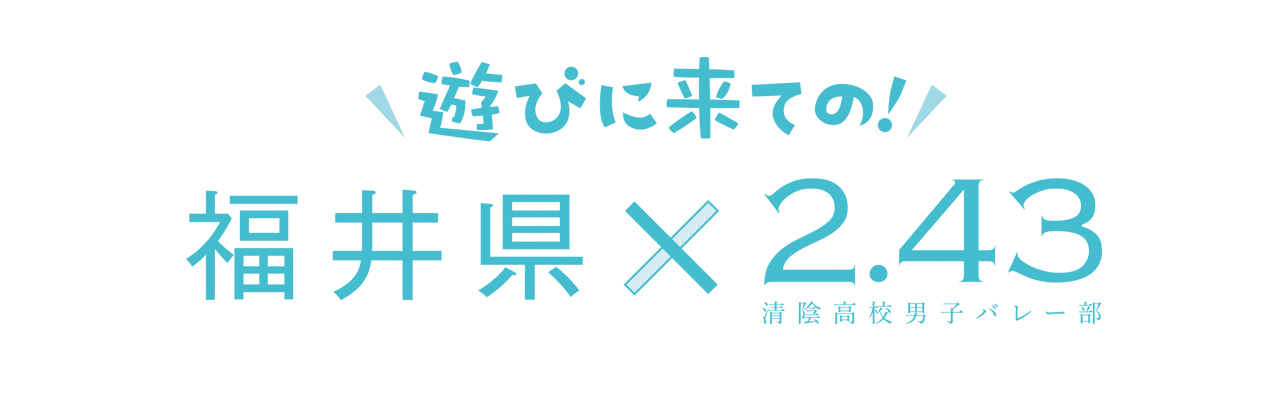たまの練習オフの翌日は、部室に来るのが一日あいただけでプレハブにこもった臭いにあらためて気づく。男子の集団特有の鼻をつく汗の臭いや、ボールやシューズのゴムの臭い。連日一緒にバレーボールをしているチームメイトと顔をあわせるなり「昨日なにしてた?」という話題になるのも新鮮味がある。
「おれは親戚のおんちゃんに朝から鮎釣りつきあわされて、休むどこやなかったですよー」
せっかくの休みの朝に喧しく叩き起こされて軽トラに担ぎ込まれた恨みをこめて
「
その灰島は「おれは昼まで寝てFIVB(国際バレーボール連盟)のチャンネルで動画見て自主練したくらいですね」と、昨日昼まで寝たくせにまだ寝足りないのかあくびを漏らして練習Tシャツに頭を突っ込んだ。
「人の誘い断っといてマイペースやな……」
「先輩たちは昨日なにしてたんですか?」
黒羽の問いに、
内村が「ほんで
棺野が「しゃあないで
「うわぁ、無意義ぃー……」
なんだかんだで自分が一番有意義な休日を過ごした気がしてきた。
「エルパでほんな偶然会いますかね?」
「ボンボンにはわかるまい。他に行くとこねぇんや」
二年生四人がしみじみと頷きあった。
エルパは福井市にある大型ショッピングモールで、衣料品店、書店、フードコート、映画館など学生が行く店舗がひととおり揃っている。清陰高校から福井駅までは電車で三十数分。清陰高生にとって休日に繰りだす遠すぎず近すぎずの「都会」が県庁所在地の福井市街である。
「エルパで見られてつきあってんのバレた奴ら、おれが知ってるだけでクラスに三組いるしな」
「バレて欲しくてエルパでいちゃついてんやろ。絶対誰かに会うの避けれんのわかってんやで」
「おれも中学んとき元カノと遊ぶん結局エルパやったなあ。映画も買い物も茶ぁするんもエルパで済んでまうでな」
「しなーっとマウント取りましたね、内村先輩」
彼女いない歴が年齢と一致するその他全員が非難の目で内村を睨んだ(灰島も間違いなく「こっち側」だが、眼鏡がTシャツの襟首に引っかかって頭をだせずにもぞもぞしていた)。
「
大隈が飽き飽きしたようにぼやく。「百回は盛りすぎやないんですか」とは言ったものの小さい頃から数えると黒羽も芝政ワールドのプールには百回行ったような感覚はある。
「
と、意外なところから声があがった。着替え中の部員の無駄話を咎めるどころか話に加わってきたのは誰かと思ったら小田だった。
「小田先輩、まさかそれデートで行ったんですか!?」
灰島を除いた後輩一同の興味津々のまなざしが小田に移った。「まさか」を強調するのが失礼極まりないが、「まさか」に後輩一同の主な感情が集約されている。
「
期待外れというかある意味期待どおりの真相に「あ、やっぱり。ほらほーですよね」とこれもだいぶ失礼なリアクションが起きた。
「小学生んなったで遠出しやすくなったっちゅうてな。逆にうちに遊び来たときは池田町のアウトドアで一日遊べるとこ連れてったりしたな。アスレチックとかラフティングとかキャンプとか……あそこもわりと新しいはずやでみんなまだそんな行ってえんのでねぇんか」
「子どもと海水浴とかアスレチックとか、どうせおまえが一番張り切って楽しんだんやろ、
と、含み笑いとともに小田の向こうで着替えていた青木まで口を挟んできた。
「かなわんなぁ、青木には。否定できんわ」
「子どもらも飽きんやろし、おまえが父親になったとこは想像しやすいな」
ロッカーを向いて左手首の腕時計のベルトをスマートに外す青木の背中がおとなびていてちょっと羨ましい。手首でボールを受けるスポーツをしていることもあって黒羽は腕時計が習慣づいていないが、制服にはいつも腕時計をしているのがいかにも青木だ。
「まあ家族でやったらいいんやろけど、嶺南も池田町も車ないとなかなか足のばさんし、デートやったらハピリンにプラネタリウムができたやろ。今年はもう終わってもたけど
青木が並べ立てたデートプランが意外にスタンダードだったので後輩一同が
小田だけが単純に感心し、
「青木が立てたプランやったら隙なさそうやし、完璧なデートやったんやろな」
「いや待て伸、なんか誤解してるみたいやけど経験談とはひと言も言ってえんぞ」
なんだかんだ小田と青木が互いを一番買いかぶりあっている。「知ったかぶりしてるだけですよね、青木先輩」黒羽がこそっと内村に囁くと、おそらく唯一の経験者である内村が余裕をかましてもっともらしく頷いた。「理想論言っても現実は結局エルパになるだけやのにな」「どんだけエルパ言うんですか」
「棺野にはアウトドアよりこういうとこのほうがいいやろって思ってな」
「ちょっ、青木先輩っ……おれをだしにしないでください」
とってつけたように青木に話を振られて棺野が迷惑そうに抗議する。大隈が無神経にからかうともっと冷たくあしらわれるが権力が違うので青木に対しては抗議が弱い。
「屋内やったら恐竜博物館もあるな。一日いても見るもんあるし」
「恐竜博物館も百回行ったけどなあ。発掘体験したときのシダ植物の化石も持ってるぞ」大隈がまたぼやき、
「おれもなんか貝の持ってますー」黒羽も追随する。
「おれは希少なん掘りあててもたみたいで持って帰れんかったですね」と棺野。
「鉱物の展示なんか今あらためて見ると小中学生んときとは違う面白さもあるぞ、あそこは。
「黒羽んちも山の中で意味不明にでかいしほぼ忍者屋敷ですよ」これはずり落ちた眼鏡をかけなおしながら灰島。
「
「ってもうデートまったく関係ねぇー。完全に社会科見学のコースやないですか……」
「東尋坊の崖で押しあいはまあ全員絶対やってますね……」
「眼鏡なんてパンツと同じようなもんじゃないですか」
「……ちょっといいか?」
と、後輩たち全員から口々にあがる消極的な声を無視して立て板に水で喋っていた青木がこめかみを引きつらせて話を中断した。
「さっきから端でぼそぼそ言ってる歴史と文化と情緒の感受性ゼロのそこのバレーバカをなんとかしろ。体育館以外に連れてきがいがなさすぎる」
「ははは、灰島ははよ練習行きたいんやな? ほしたら無駄話はこんくらいにして移動すんぞ」
小田が笑って号令をかけた。「へーい」「行きますか」と不揃いな応答があがり、ボール籠などの用具を分担して部室棟の狭い通路へぞろそろと移動がはじまった。
「プラネタリウム……花火大会……うーんでも
入ったときに気になった部室の臭いには喋っているうちに嗅覚が慣れ、意識してもほとんど知覚できないくらいのいつもの「匂い」になっていた。
生まれた頃から行き飽きた場所も、今度は誰と一緒に行くかを想像したら新鮮かもしれないと、小田や青木や棺野を見て黒羽は思った。
「今度恐竜博物館でも行かんか? おれは百回くらい行ったけど、おまえ行ったことあるけ?」
灰島の横に並んで話しかけた。灰島は小学校にあがる前に東京へ引っ越し、福井に帰ってきたのは中二の冬だ。黒羽は小中の校外学習で飽きるほど行ったが、その思い出の中に灰島はいない。
ところが返ってきたのは予想外の答えだった。
「行ったことあるよ。一緒に」
「へ? ほやったっけ?」
「おまえんちのおばさんに連れてってもらったんじゃねえか」
昔一緒に遊んだ頃の思い出に関して灰島は淡泊な態度しか見せたことがない。自分のほうがよく憶えているという優越感みたいなものがあったので、灰島が憶えていて自分が憶えていないことがあったとなるとなんだか悔しい。
「おまえが飽きて外の遊具んとこで遊ぶってゴネたんじゃん。それでおまえ、外行って迷子になって」
「あっ、待て、思いだしてきたぞ……!」
駐車場から見えた大きな遊具が気になって黒羽はずっとそわそわしていた。博物館の外にも恐竜をモチーフにした滑り台などの遊具がある広場があり、館内に入らずとも子どもが一日飽きずに遊ぶこともできるのだ。母親に駄々をこねて外に行ったのだが、夢中で遊んでいるうちに灰島の姿がなくなっていた。
案内所にも通報して館外の捜索がはじまったが、なにしろほとんど山一つが
外を捜してもいないわけで、灰島は一人で館内に戻っていたところを発見された。しかも別に見つかりにくい場所に隠れていたわけでもなく一番人目があるメインの展示室が発見場所だった。
黒羽が母親と駆けつけたとき、灰島は係員と手を繋いでティラノサウルスロボットの前にいた。
恐竜時代を体感できる広大なドーム型の展示室だ。中生代の風景が再現されたジオラマを背景にリアリティたっぷりに動くティラノサウルスが首をもたげ、恐ろしげな咆吼が響きわたると、臨場感ある演出に親にしがみついて泣きだす子どもも多くいた。灰島は泣きだす以前に驚きのあまり声もだせず、小さい頭が転げ落ちるんじゃないかと思うほどめいっぱい上を向いて、かつて地球に君臨した巨大生物の迫力に魅入られていた。迷子預かり所に連れていこうとしても頑としてここから動かないらしく、係員が苦笑してつきあってくれていた。
決して感受性が乏しいわけではない。灰島の興味は幼い頃から一点集中型なのだと思いだすとともに、ああなんだ、そうだった……と、思いだしたことがあった。
たいてい
あれは単に黒羽の中のイメージではなくて、過去に本当にいた灰島だったのだ──。
「……って、思いだしてみたら迷子になったんおれやなくておまえやろげ!?」
「おれは迷子になってない」
「それ迷子の自覚なかっただけやろっ」
「いーや。なってない」
「認めろや……あっ、逃げた!」
体育館が行く手に見えてくると灰島は待ちきれないように前のめりになって駆けだしていった。
もし灰島が東京でバレーボールと出会わなかったら、もしかしたら恐竜の研究者にでもなっていた未来もあったのかもしれない。ともあれ今の灰島の興味の対象はバレーボール一点だ。
溜め息をついて黒羽も足をはやめた。