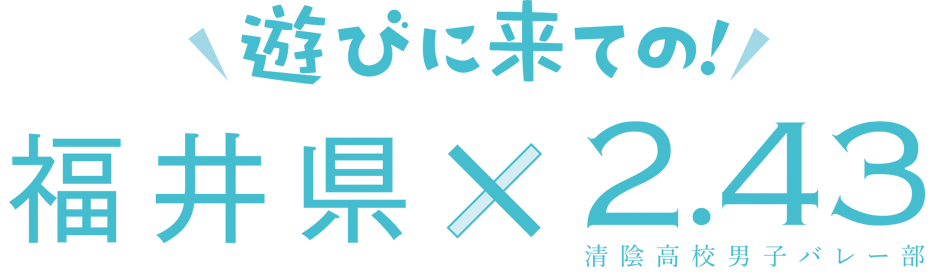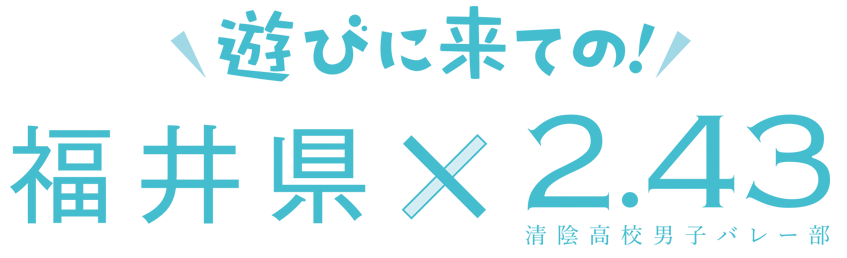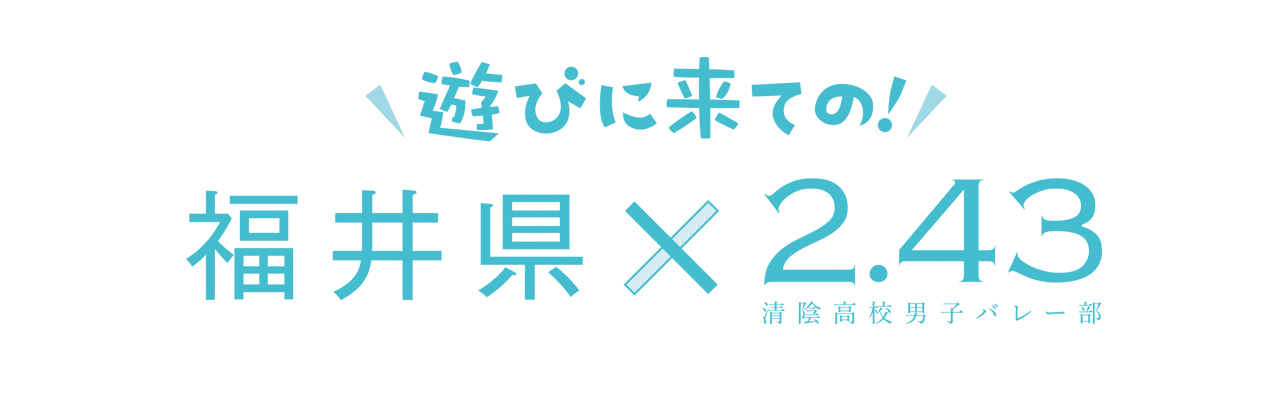幼い頃は喋っていた福井弁が
母を亡くしてまもなく福井から引っ越し、翌春には東京で小学校に入学した。福井出身ではない父は福井弁を話さなかったし、父と二人暮らしのマンションと小学校の往復という生活範囲で福井弁を耳にする機会がまったくなくなると、灰島も自然と東京の言葉を話すようになった。もともと無口な子どもだったから、言葉が舌に根づかないうちに福井を離れたことも大きかったのだと思う。
それでも仏壇の中にいる母の遺影と話すときだけは長らく福井弁だった。マンション向けのコンパクトな仏壇が父の寝室のクロゼットに収まっている。帰宅すると父のベッドに飛び乗って”おちょきん”し、仏壇と向きあって「お母ちゃん、今日はの……」とその日のことを母に話した。遺影の中でいつも優しげに微笑んで、ほうなんか、よかったの、がんばったんやの、ほれは悔しかったのぉ、などと相づちを打ってくれる母の声も福井弁だった。
しかし学年があがるにつれ遺影に話しかける時間は減っていき、心の中での呼称も「お母ちゃん」から「母さん」や「おふくろ」に変わり、やがて一日一度遺影をちらと見るだけになり、そうして唯一灰島が福井弁を話す時間もすっかり消失した。
そのことに寂しさは別に感じない。それは地区の小学生のバレーボールクラブに入り、身体を動かしたりバレーボールのことを考える時間が増えていった時期とちょうど重なっていた。生活範囲が広がって、心を占めるものの割合がいい意味で変わっていっただけだった──。
「みんなかしこまらんと、おちょきん崩していいでの」
離れに料理を運んできた
ウーロン茶を注いだ人数分のグラスがテーブルの上でまわされる。表面張力で耐えうる限界まで琥珀色の液体が満たされたグラスを「おっとっと、つるつるいっぱいやげ」と小田が慌てて口で迎えにいってすすると「小田先輩オヤジくさー」と笑い声があがる。
不思議なもので福井弁はもう自分の中にないと思っていたのに、こうして耳で聞く福井弁は頭の中で標準語に翻訳せずとも福井の言葉のまま自動的に理解できているので、会話にも生活にもなんの障壁もないのだった。
カニがようけ届いたでバレー部の皆さんも呼んだらって言われましてー。
と黒羽に招かれ、カニにありつけるならと一も二もなくバレー部一同で招きにあずかって部活帰りに黒羽邸にあがり込むことになった。福井県北東部の
「おばさん、この油あげうまいですね。あとこの里芋の煮っころがしも。ていうか全部うまいです」
「田舎のもんばっかやけど、ほーやって若い子らにたくさん食べてもらえるとおばさんも嬉しいわあ。広間のおんさんらはお酒飲んで喋ってばっかで箸伸ばしてくれんでねえ」
大皿に盛られた郷土料理に八方から箸が伸びてハイペースで減っていく。運動部男子高校生八人の気持ちのいい食いっぷりに黒羽の母はまんざらでもなさそうだ。
分厚い油あげはだしをたっぷり含んでいた。たくあんの煮たのを口に含むと、中学二年で福井に戻ってきた頃、祖母がこしらえたものをひさしぶりに食べた瞬間驚いた記憶が蘇った。東京で食べ慣れていたたくあんのしゃきっとした歯ごたえを想像して口にいれたので脳が錯誤を起こしたのだった。
二畳分ほどもあるテーブルに所狭しと並べられた料理が八つの胃袋にほとんど消えた頃、
「お待たせー。今日の主役の登場やよー」
黒羽の従姉妹である
「よっ、待ってまし……」
湯あがりの朱に染まった、
大皿の外周に脚やハサミがわさわさとはみだし、キャビアみたいなカニビルが甲羅に貼りついたその威容に二年や三年が目をみはってたじろぐ中、黒羽が平然とその一匹──食べるカニの単位だと一杯の甲羅をわしづかみにした。当然みたいに一杯まるごとを自分の皿に移した黒羽にどよめきとともに信じがたい目が向けられた。
「カニようけ届いたって、越前がにのほうやったんけ……!?」
「うちは
「ほら普通はせいぜいせいこが一人一杯やろ……」
「こらっ
絃子にぴしゃりと叱りつけられて黒羽が首をすくめた。「みんな遠慮せんと取っての」と絃子に勧められ、まずは小田が、続いて青木や二年が恐縮しつつ手を伸ばした。
大皿に残った最後の一杯に灰島も手を伸ばした。海岸の岩場で両手いっぱいの岩を掴むみたいな、ずっしりした厳つい甲羅を手もとに移しつつ隣に目をやると黒羽が虫も殺さないような顔で脚をばきばきと折っている。脚の中に詰まった身を黒羽が慣れた手つきで吸いだし、ひと口で一本分を頬張った。
灰島が暮らす祖父母の家でも冬になるとカニが食卓に上るが、やはりメスの”せいこがに”のほうだ。オスの”越前がに”は福井でも高級品扱いなのでそうそう頻繁に食べる機会はない。越前がにより小ぶりとはいえ胴体が拳ひとつほどはあるせいこがにが一人一杯食卓に上るだけでも東京だったら驚かれることだが。
中学で一人一杯せいこがにを自分でほぐして食べる授業があったためカニの食べ方は全員一応は知っている。やや四苦八苦しながらも大ガニの脚をもいで身を取りだしていく。そのあいだに悠々と脚を全部処理した黒羽が次に胴体をひらき、中に詰まったカニ味噌に脚をたっぷりとひたしてまたちゅるりと食べる。普段のほほんとしていて時に苛立たされる面構えがなんだか今日は大物に見えてくる。
「あらためてこいつ、ボンボンやったんやな……」
「毎日カニ食えるんやったら黒羽の嫁んなってもいいわー」
などと言いだした大隈に乗じて、
「カニのために黒羽に身ぃ売れる奴は?」
と青木がアンケートを採った。大隈、内村、
「おまえまでか、
「いやまあ、カニには一瞬負けそうになるな」
青木が半眼になると小田が気まずそうに照れ笑いする。
「ていうかおれにも拒否権ありますって。嫌ですって全員」
黒羽が口を尖らせて抗議した。
*
家が広いぶん遠いのが難点な手洗いに行って戻り際、危なっかしい足取りで廊下を歩いている絃子の後ろ姿が見えた。両手で運んでいる銀の盆に大量のビールの空き瓶が剣山のごとく載っている。絃子の小さな悲鳴とともに空き瓶がぐらつくのを見て灰島ははっとして床を蹴った。
追いついて滑り込むように片手を伸ばし、傾いた盆の端を間一髪で支えた。キュッと靴下がよく磨かれた板張りの床を擦った。「っと」盆の端から転げ落ちた空き瓶をもう片手で危うくキャッチ。盆の上で瓶が何本かがちゃがちゃと倒れただけで済んだ。
ふう、と息を抜いた。
「灰島っ……?」
身をすくめた絃子が振り向いて目を丸くした。
「ありがとのー。ひやっとしたわー。さすがレシーブも巧い選手やねえ」
「逆にバランス悪いから手離して」
礼を遮って絃子から盆を引き受けた。「調理場のほう?」と歩きだすと、ちょっと
昔はよく遊びにきていたので黒羽邸の見取り図は頭に入っているが、知らない部屋や廊下を未だ発見したりするので全貌は灰島にもあきらかではない。極秘で町の外に脱出する地下道とか絶対ある。
低い天井に間隔をあけて吊り下がった裸電球が照らすだけの廊下は仄明るく、ひえびえした黒褐色の床が闇に消え入るまで続いている。アルコール臭が廊下にまでうっすら漂い、年配の男たちの賑やかな談笑の声がくぐもって響いていた。今日は大広間に黒羽家の親戚たちも集まっているらしい。おんさんたちの宴会に同席させられても気詰まりだろうと、バレー部の席は離れに用意してくれたのだ。
「座って食わねえの」
と、歩調をゆるめず端的に訊いた。
斜め後ろをついてくる絃子がきょとんとし、
「気ぃ遣えるんやの、灰島。ちょっと意外やわー。あっごめん、気ぃ遣えんって意味やないけど」気ぃ遣えねえって意味以外のなんなんだよ……別に言い返さなかったが。
「あとでおばちゃんたちといただくで大丈夫やよー。今年は本家でやってるでおばちゃんたち忙しいけど、いつもはあわら温泉の旅館でカニの会するんやよ。そんときはおばちゃんたちものんびりしてるし」
「よくしょっちゅうこれだけの人数が集まるよな、ここんちは」
「あはは、ほやのぉ。春になったら
住んでいるのは本家の家族と数人の住み込みの人間だけなので部屋数のわりに人口密度は異様に低い家だ。人がおおぜい集まるときは本宅の台所ではなく調理場で煮炊きが行われる。離れと本宅を繋ぐ建物にちょっとした小学校の給食室くらいの設備の調理場がある。
調理場では黒羽家の女たちがかしましく話しながら立ち働いていた。
冗談にしたってあいつの嫁に来るっていうことの意味がわかってんのかな……と、さっきの大隈や青木の話をちらりと思いだした。
「おう」
と、盆を置いた調理台の端からふいに声をかけられた。
女ばかりの調理場に男が一人、縦も横もがっしりした体躯を窮屈そうに簡易な丸椅子に落ち着けてカニを貪っていた。
「
と絃子が三つ年上の兄をぞんざいに名前呼びし、ビール瓶を抱えて片づけにいった。
「宴会はじじいに出禁食らっててな。昔本家からカニ盗んで一杯一万で売ったんがバレて」
悪びれるどころか武勇譚を誇るように頼道が言い、厚みのある背中を丸めてカニの脚を端からぷっと吹くと反対側からつるりと身が飛びだす。大ガニを器用に食べる様は黒羽と同じく熟練している。
「一万って、ぼったくりじゃ……」
「あほか。おまえらが食ったカニの値段知ってんけ。一杯三万はくだらんぞ」
「え」と低い声がさすがに口からでた。先ほどまるごとしっかり食べ尽くしたカニが胃の中で三万円分の重さを主張した。
頼道がにやにやと野卑な笑いを浮かべ、
「タダでは帰れんのぉ。腎臓の一つくらい置いてかんと」
「もぉ、あほ言ってえんと! おじいちゃんに言いつけるよ」
「カニの値段はほんとやげ」
絃子の声が飛んでくると頼道が口を尖らせて言い返しつつ首をすくめた。黒羽と雰囲気はまるで似ていない従兄弟だが、さっき同じように絃子にぴしゃりと言われたときの黒羽とそんな仕草は妙に似ていた。
「ま、ほーでねんなら祐仁にツケとくで、祐仁がこの家継いでから出世払いしてもらわんとな」
「やっぱり黒羽がこの家継ぐんですか」
「ほらほやろ」
頼道にもその権利がないわけではないはずだが、自分を百パーセント除外しているような即答が返ってきた。
「本家のひとりっ子やで、祐仁は親戚中から可愛がられてな。やれ夏は釣りだの冬はスキーだの、おんさんらの誰かになんやかや連れまわされて、体験だけはいろいろやってきたんに……結局夢中んなったんがそのどれでもなくて、バレーボールとはな」
調理場のどこからか頼道が一升瓶を持ってきた。身と味噌がいくらか残った甲羅の中に片手で掴んだ一升瓶からとぽとぽと透明な液体を注ぐ。
灰島とは一度もはっきり目をあわせないまま、溜め息まじりにぼそりと。
「……妙なもんやな。おまえとはぜんぜん違う育ち方したはずなんに」
器がわりにした甲羅に口をつけてすすろうとしたところを「こらっ、こっそり食べさせてやってるんに贅沢な飲み方しなさんな」と、頼道の母が取りあげた。
「なんじゃばばぁ、返せや」
「まったくあんたは、こういうことばっかおんさんらから吸収して。ちょっとはあんたもなんかスポーツくらいしねや」
「うっせぇのぉ、あれはすんなこれはしねって……」
息子と母のやりあいになるとつきあう義理もないので灰島は調理場をあとにした。
*
「遅かったな灰島」
離れの座敷に戻ってくると「家ん中で迷子んなってたんやろ」「捜しいこうって言ってたとこやぞ」と奥の席から二年がからかい口調で言ってきた。戸口側に座っている黒羽が身体をねじって振り向き(今の話を聞いてきた直後だといずれこのお屋敷の主になるこいつを下座に座らせていいのかと思わなくもない)、
「灰島、スキーやったことあるけ? 積もったらみんなで
とちょうど頼道の話とかぶる話題を振ってきた。
「はめ外して怪我せん程度にな」
小田に釘を刺されて黒羽が朗らかに「はーい。わかってますって」とほんとにわかってるんだか怪しい二つ返事をする。「けっこう滑れるとこ見せますよー。ちんちぇー頃からよう連れてってもらってたんで。あと桜咲いたら花見もあるんで、たぶんまた部のみんなに声かけるように言われますよ」
「桜咲く頃にはおれらは卒業してるわ」
青木が淡泊に指摘すると甘ったれたような顔で眉尻を下げ、
「えっ。寂しいこと言わんでくださいよぉ」
「卒業させん気けや」
悪く言えば甘ったれののんびり屋で、よく言えば朗らかで情緒が豊かで……こいつがこういう人間になったのは、まわりから愛情を惜しみなく注がれて福井の四季の中で育てられた環境がたしかに下敷きになっているのかもしれない。頼道の話を思い起こしてあらためて灰島はわかったような気がする。
頼道に言われたとおり、自分とは対照的な生育環境だ。
「今食ったカニの値打ち、一杯三万くだらないそうなんで、黒羽がこの家継いでから出世払いだそうです」
黒羽の隣に座りなおしながらみんなに言った。
「三万!?」
黒羽以外の全員が目を剥いたがもちろん時すでに遅しである。しまった、という顔でとっくに綺麗に食べ尽くして殻が残るだけになっためいめいの皿を見下ろした。自分だけが頼道に驚かされるのは癪に障るのでちょっと胸がすいた。
「大丈夫ですって。ほんなぼったくりバーみたいなことせんですって」
「おれは出世払いするから。黒羽が家継ぐのを待たなくても、来年の一月には」
先輩たちを安心させようとした黒羽の声にかぶせて灰島は言い切った。
「春高に行く。春高のセンターコートでおれが黒羽を世の中に知らしめる──”黒羽を出世させる払い”で清算する」
対照的な環境で育って、東京と福井で異なる四季を見てきた黒羽と、同じものに本気になって、肩を並べて同じ場所を目指していることを、数奇な巡りあわせだとは灰島は思わなかった。なるべくしてなったという確信しかなかった。バレーボールは世界で一番面白いんだから。
ふんぞり返るような態度で灰島が宣言すると黒羽がたじろいだように身を引いた。目をぱちくりさせたが、
「ほれで三万じゃ、こっちがお釣りださなあかんわな。大出世や」
と、最近備わった頼もしげな顔で笑った。