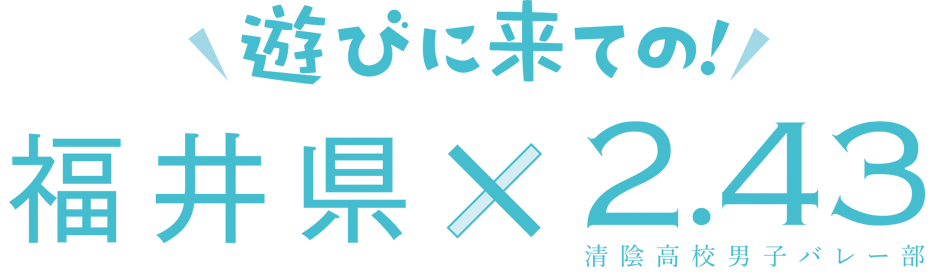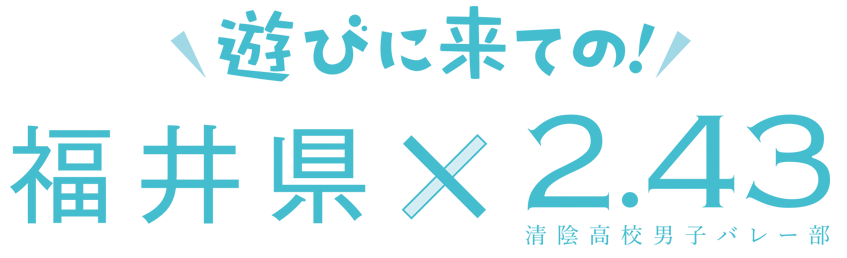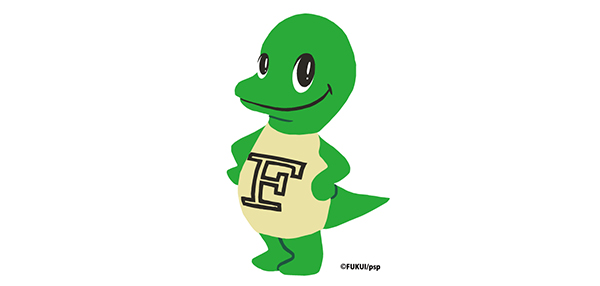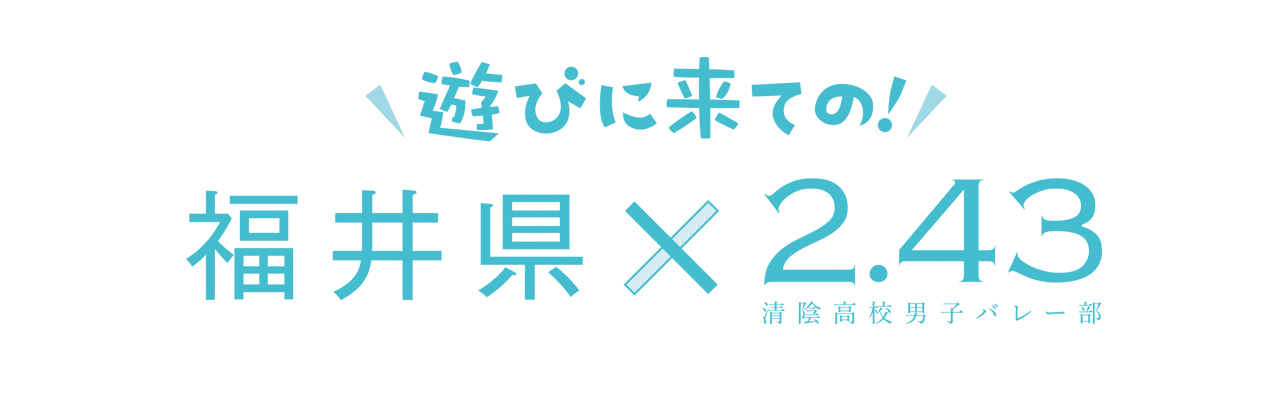これは
「親の車で県外行ったときの話なんですけど、高速でサービスエリア寄ったんです。ほんでフードコートでカツ丼の食券買ったら……なにがでてきたと思います? 親子丼やったんですよ!」
「おまえの注文が間違ってたか、店の人が間違ったかのどっちかでねぇんか」
「食券は間違ってえんかったですよ。ほんでカウンターん中の人にも聞きましたよ、カツ丼頼んだんですけどって。ほしたら変な顔されて、はい、カツ丼注文されてますねって。会話んなってえんですよね?」
「? どーゆうことや?」
おざなりに聞き流していたバレー部の面々が戸倉の話に次第に興味を引かれてくる。もったいぶった顔つきで戸倉がテーブルの上に身を乗りだし、
「
「わからん。ほんとやったらたしかに妙な話やな」
まさに
「ほんとの話なんですって! ほんでもう話通じんし、親子丼でもいいわって思って持ってって、食ったんですよ。ほしたらまあ、カツはカツやったんですよ。ただトンカツにするあっちのカツですよ、肉が厚いやつ。トンカツが親子丼みたいに卵とじになったやつを、そのサービスエリアではカツ丼っちゅうてだしてたんですよ」
「ほんなあほな」
戸倉の熱弁に引き込まれて聞いていた部員たちがどっと嘲笑し、興味を失って箸を進めはじめた。
「工兵にしては途中までわりとよかったけど、オチがつまらんなー」
と三村も薄切りのカツレツにかじりつく。パン粉の目の細かい揚げ衣が口の中でさくさくと繊細な音を立て、衣に染みたウスターソースの味が広がる。白飯にかかったソースも絶妙だ。
「統先輩までー! 実話やでオチがつまらんのはおれのせいやないですって」
土曜の部活帰りの午後だった。昼食どきを過ぎ、夕食どきには早いので学校から一番近いヨーロッパ軒は幸い空いていた。大衆食堂らしい趣の化粧板のテーブルは練習後の空きっ腹を抱えて押しかけた福蜂バレー部員で占められている。
「……さて」
全員の丼が空になった頃を見計らい、三村はおもむろに立ちあがった。厳かにテーブルに両手をつき、まわりのテーブルを見まわして。
「今日これから有志を募る」
重々しく切りだした主将の声に、胃袋が張るのに比例して弛緩していた部員たちの顔に緊張が走った。
「もしかして練習戻るんか? 今日の練習でなんか気になったことでもあったか」
マネージャーの
「とうとうこの言葉を口にする日が来た」
生まれて十七年来夢に見た……というのは大袈裟でまあこの一年くらいだが、話題になりはじめてからずっと憧れていたフレーズは、口の中ではじけるようなくすぐったい語感だった。見聞はしていたが、自分の舌に乗せるとこういうものかと感動がこみあげた。
「タピりにいきたい」
*
「半分しかついてきてくれんかったー」
「半分もついてきたことにおれは驚いてるわ」
二十数人から半分に減った面子を見渡して嘆く三村に越智があきれて言った。
「それにしても知らんうちに福井にもできてたんか。しかも三軒もやってか?」
「福井舐めんなって。一軒目はけっこう前にできてたんやって。ほやけどずーっと行列できてたで指くわえて通り過ぎるだけで、最近三軒目できてやっと人もばらけたやろって、練習午後で終わるし今日を決行日にしようと」
「よー喋るなおまえ……。そんな上機嫌なんもあんま見んくらいやわ。おまえの甘党、ある程度キャラ作りなんかと思ってた時期がおれにもあったわ……」
「甘いもん飲み来たんにそんな苦いテンションで興削ぐなやー」
小言が多い越智に三村は口を尖らせる。しかし消極的姿勢ながらも絶対つきあってくれるのが越智でもある。はめを外さないように手綱を締めるためでもあるのだろうが。
三村の嗜好についてきてくれた十数人のバレー部有志が黒い学ランにエナメル地の赤いチームバッグを肩にしょったまま店の外でプラスチックのカップを手にし、極太のストローに物珍しげに口をつけている。店の中から延びている行列はそれほど長くはないが、三村たちが買ってからも絶えず最後尾に人がついて減ることはない。「チアダンの子ぉらですかねえ」と戸倉が囁き、きりりと髪をひっつめておだんごにしたきらきらした女子高生グループに見惚れたような視線を送った。
圧倒的に多いのは女子高生だが、老若男女が浮き立った表情で並んでいる。
「うまくストローに入ってこんな……」
「こうや、こう。おれの見本みてみ」
戸惑う部員に三村は得意げに言ってカップの底に溜まったタピオカを吸いあげた。口に飛び込んできた弾力のある粒が喉まで到達して危うくむせるところだった。
「おまえかって初めてやろが、統。一人で並べんでみんな引き連れてこんとでかい顔できんのやろ」
体裁を繕ったのにつきあいの長い三年には見抜かれていた。
「おまえらも来てみたかったんやろ。工業高校生、みんなミーハーの引っ込み思案か」
越智の鋭い洞察に最終的には全員反論できない。
「おれにはちょっと甘すぎやわ……。しょっぱいもんを口が求めるな」
「おっ、ほしたらラーメンでも食って帰ろっせ。今から8番行く奴ー?」
「待てや、カツ丼食ったばっかやろっ」
ぎょっとしてとめようとした越智の頭の上で三村が募ると、「行きまーす」「おお、いいな。おれもしょっぱいもん欲しなったとこやし」と次々に名乗りがあがった。
*
「さっきの話の続きしていいですか? 親の知りあいいる長野行ったんですよ。ほんで福井も蕎麦処でしたよねーってその家で蕎麦ふるまわれたんです。あっちはざる蕎麦が基本なんすね。箸で蕎麦すくってつゆの器につけて食うやつ。おろしも薬味と一緒にちょこっとついてるくらいのやつで。蕎麦っちゅうたらぶっかけのおろし蕎麦を丼ごとすすりたいですよねぇ?」
駅ビルの8番らーめんで味噌、塩、しょうゆ、とんこつなどと好き好きに注文し、戸倉の話を右から左へ流しつつ時間を潰しているうちに、渦巻き模様のなるとのかわりに『8』と書かれたかまぼこがてっぺんに鎮座したラーメンがめいめいの前に順次提供された。
三村はこのハチカマを真っ先に食べる派である。太麺の上にたっぷり盛られた野菜とハチカマを箸で大きくすくって最初のひと口を頬張る。
「あ、
高杉と朝松の丼からはスープに溶けたバターのいい香りが漂っていた。一気にすすった太麺で口をいっぱいにした二人がもごもごした声で「ほあ」と頷いた。
「おれ味噌にしたけど一瞬迷ったんやってー。二杯目いこうかな。いや餃子つければよかったな」
「二杯目いくならつきあいますよー」
「おれも餃子頼むかな」
はやくも麺を減らして未練がましくスープの中を箸で掻きまわしだした部員たちからも賛同者が現れ、手持ちぶさたにコップの水を飲んでいた越智が口に含んだ水を噴きかけた。
「正気かおまえら!? タピオカかってけっこう腹に溜まるやろ!」
「タピオカで腹膨れるわけないやろ? ほぼ空気やげ」
部員たちに素朴に不思議がられて「がっつり炭水化物やぞ……」と越智が頭を抱える。
「まあここは一杯でやめとくか」
三村の声に救いの手を差しのべられたように越智がほっとした顔をあげた。「ほらほやろ。統がとめてくれて助かったわ」
レンゲでスープを最後まですくって飲み干してから、にこやかに三村は言った。
「かわりに焼き鳥買ってこっせ」
「統ー!?」
*
「純けい五本とねぎま五本、おみやげでー」
「はい、いらっしゃいませ!」
「あ、あと串カツも五本ー」
駅前の
西口ロータリーにぐるりと囲まれた植え込みの前にベンチが据えられたスペースがある。ベンチの真ん中の席にちょこんと座っているラプトくんの人形の頭に挨拶がわりにぽんと手を置き、三村はその隣に腰をおろした。
と、背後で獣が唸るような低い声が聞こえた。
植え込みの中だ。なにか大きな影が動く気配がし、うろこ状の皮膚に覆われた太い脚がのそりと覗いて――。
体高数メートルに及ぶ恐竜が三体、ゆったりと巨体を揺らし、つぶらな目玉で周囲を牽制するように見まわして、暮れはじめた空を引き裂くような鳴き声をあげた。
が、驚く部員は一人もおらず、ギシギシ動いている恐竜を尻目に焼き鳥に舌鼓を打ちはじめた。
「知ってます? 恐竜って爬虫類の祖先やなくて、鳥類の祖先なんですよ」
「焼き鳥食ってるときにする話けや」
県外エピソードは尽きたのか戸倉がひねりだした話題にぞんざいな突っ込みが入るが、周囲の状況には誰一人突っ込まないので、
「
と越智が顎で植え込みの中を示した。
フクイラプトル、フクイサウルス、フクイティタン。いずれも正式に福井を冠した学名がつけられた福井産の恐竜である。西口ロータリー名物・三体の恐竜のモニュメントが夕空の下でライトアップされる時間だ。
「まあ全員いっぺんはあそこで襲われそーになってるていで写真撮ったことはあるやろけどなー」
と、三村はベンチの背もたれ越しに福井駅舎を振り返った。
駅舎の壁には《ダイナソーキングダム・フクイ》という看板文字が掲げられ、壁を突き破って襲いかからんとする恐竜のトリックアートが描かれている。すでに見慣れた風景だが、できたときはみんなで面白がってふざけたものだ。
串に通った焼き鳥をあんぐりとくわえてまとめて抜き取り、ひと口で一本食べた。
「今日は散財してもたなー。やっぱだいぶ腹いっぱいになってきたし」
「おまえの満腹中枢無事で安心したわ……。なんで最後に焼き鳥買うなんて言いだしたんや」
「なんか帰るの惜しなってなー。みんなで買い食いするん楽しくて」
越智がすこし驚いたように口をつぐんで三村の横顔を見つめてきた。
「工兵ー。もっとなんか他の話もあったらしてー」
「どーせおれの話はオチつまらんですよー」
「むくれんなって。つまらん話でいいざー」
ことごとく雑に扱われて拗ねていた戸倉に三村は甘えた声でねだった。
「聞く前からつまらんってはっきり言わんでもいいでしょ……。ほしたら長野行った話の続きですけど、飯食ったあとなんでタラの子の缶詰でてきたんや?って思ったら、水ようかんやったんですよ。缶に入ってる水ようかんやったんです。冬の話やないですよ? 夏に水ようかんって食います?」
「あ、ほーいや水ようかん昨日親が買ってきてあったで帰ったら食わんとー。カニ解禁したで水ようかんもやっと解禁やー」
「カニと水ようかんの解禁おまえん中で同じ重要度なんか」越智が半眼で言ってから「って腹いっぱいなんでねぇんか!?」と目を剥いた。
「水ようかんは飲みもんやろ。ひと箱くらいつるっといけるわ」
買ったからには残す気もないので焼き鳥も残さず食べる。ひと串が小ぶりなので満腹でも五本や十本は余裕で胃に入る。
「こんだけ食ってもぜんぜん肥えんの今だけやぞ、っちゅうんは覚えとけや……。本気で頼むでおまえ、三十とか過ぎてもシュッとしててくれや……県民の夢壊さんためにも……」
真剣に嘆願してきた越智がふと、「今だけ、か……」と、自分の言葉を感慨深げに反芻した。
「こうやって一日中みんなでバレーやって、買い食いして帰ったりするんが当たり前なんも、今だけなんやろな……」
ほやな、と三村は頷いてベンチに深く寄りかかり、背もたれの上に後頭部を預けた。顎を反らすと冬が近づき雲が増えた北陸の空が視界に広がる。長い首を持つフクイティタンがにょきっと視界に一緒に入ってくる。これが日常的な光景になって普段なんとも思わないのもどうなのかとは思う。
小惑星の激突で絶望的な天候と化した地球の空を見あげて嘆いた太古の記憶を思いだすかのように、フクイティタンが赤味がかった黄昏色の空の下で切なげな声でいなないた。
今だけの特権なんだろう。気のおけない仲間たちとばかばかしい話をしながらあっという間に暮れていく一日も、それがなにも特別に思わないただの日常なのも。
*
「ただいまぁ」
自宅は福井県庁に近く、普段の行動範囲は自転車移動ですべて事足りる。福井では『街っ子』と呼ばれる地域で三村は生まれ育った。
居間のテレビの前に座っていた姉が「おかえりー」と振り返った。
「姉ちゃん帰ってたんか。あ、土曜か。かーさんは?」
三つ離れた姉のむつみは高校を卒業して家を離れているが、近県なので週末はちょくちょく帰ってくる。
「おかーさん遅なるでお惣菜買ってくるんでいい?って連絡あったけど、統もうおなか減ってる?」
「ちょっと食ってきたでちょうどいいわ」
自室に着替えに行く前に台所に直行して冷蔵庫をあけると、平たい長方形の紙箱が二つ重ねて入っていた。三村家では毎年なじみの和菓子店のものだ。ヘラですいっと切ってすくいながら箱ごとつるつると吸うように食べるのが冬の醍醐味である。
「飯遅なるんやったら先に食おっかなー」
『統ー!』
鼻歌まじりに冷蔵庫の紙箱に手を伸ばすと頭の中にちっちゃい越智が現れて悲鳴をあげた。
『後生やで肥えんでくれー!』
一瞬だけ手がとまったが、
「……ほやかって今だけなんやったら今のうちにー」
すばるー、と泣きついてくる越智を頭の中から追い払った。